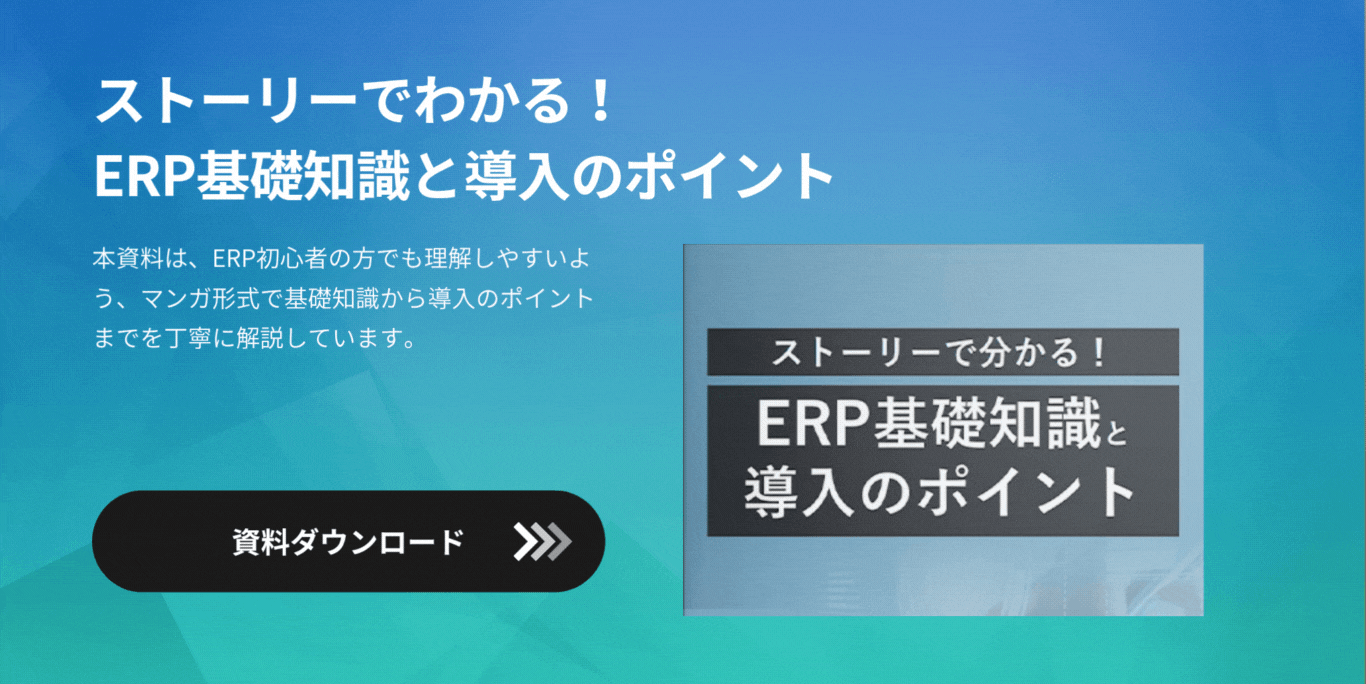企業の規模が拡大するにつれ、「現場のコスト意識が低い」「どの部門が利益を生んでいるか不明確」といった課題に直面する経営者様は少なくありません。独立採算制は、部門ごとに収支を管理し、あたかも一つの会社のように経営させることで、社員の当事者意識や収益性を高める強力な経営手法です。
しかし、適切なルール設計なしに導入すると、セクショナリズムの助長や管理業務の肥大化といったデメリットも生じます。本記事では、独立採算制の仕組みや導入のメリット・デメリット、成功に導くためのポイントについて詳しく解説します。
この記事で分かること
- 独立採算制の基本的な仕組みと目的
- 導入によるメリット・デメリットと注意点
- カンパニー制や事業部制との違い
- 制度運用を成功させるポイントとERPの活用
独立採算制の基本的な意味と仕組み

企業が持続的な成長を遂げるためには、組織全体で収益性を高める意識を共有することが不可欠です。独立採算制は、組織を細分化し、それぞれの部門が自律的に収支を管理することで、全社的な筋肉質の経営体質を目指す手法として多くの企業で導入されています。本章では、独立採算制が具体的にどのような仕組みで成り立っているのか、その基本概念と運用の要となる管理会計の視点から解説します。
独立採算制とはどのような経営手法か
独立採算制とは、企業内の事業部、支店、あるいはさらに細分化された部門を一つの「独立した会社(疑似的な企業)」と見なし、自律的に経営を行わせる管理手法です。各部門には予算の策定や業務遂行に関する大幅な権限が委譲される一方で、その結果としての「利益責任」も明確に求められます。
一般的な機能別組織(製造、営業、開発などが分かれている組織)では、利益は全社の結果としてしか見えにくく、個々の部門がどれだけ会社に貢献しているかが曖昧になりがちです。これに対し独立採算制では、部門ごとに売上と費用を計上し、採算(利益)を算出します。これにより、現場のリーダーや社員一人ひとりが「自分たちの活動がどれだけの利益を生んでいるか」をリアルタイムに意識するようになります。
独立採算制と従来の中央集権的な組織運営との主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 従来型組織(中央集権) | 独立採算型組織(自律分散) |
|---|---|---|
| 意思決定 | トップダウンによる指示命令 | 現場への権限委譲による自律判断 |
| 利益責任 | 経営層が全責任を負う | 各部門長が部門利益に責任を持つ |
| 管理指標 | 売上高や生産量などの部分的指標 | 部門ごとの損益(利益) |
| コスト意識 | 予算枠内での消化が目的化しやすい | 利益最大化のためのコスト削減を追求 |
このように、独立採算制は単なる管理手法の変更にとどまらず、現場に経営者意識を持たせるための人材育成システムとしての側面も強く持っています。市場の動きに敏感に反応し、現場レベルでスピーディーな意思決定を行うことが、競争の激しい現代のビジネス環境において重要視されています。
部門別損益計算書の重要性と役割
独立採算制を絵に描いた餅にせず、実効性のある仕組みとして運用するために不可欠なのが「部門別損益計算書」です。これは、株主や税務署へ報告するための「財務会計」上の決算書とは異なり、社内の意思決定に役立てるための「管理会計」の視点で作成される部門ごとの成績表です。
部門別損益計算書を作成する上では、以下の要素を正確に把握する必要があります。
- 部門収益:外部顧客への売上だけでなく、社内の他部門への製品・サービス提供を「社内売上」として計上する場合もあります。
- 部門個別費:その部門だけで発生した人件費や経費など、直接紐づけられる費用です。
- 共通費の配賦:本社管理部門の費用や全社的なシステム利用料など、部門単独では発生しない費用を、一定のルール(人数比や売上比など)に基づいて各部門に負担させます。
特に重要なのが、共通費の配賦や社内取引価格(振替価格)の設定です。これらが公平かつ納得感のあるものでなければ、部門間の不公平感を生み、組織の連携を阻害する要因となります。正しく設計された部門別損益計算書があれば、どの事業が真に収益を生んでいるのか、あるいはどの部門のコスト構造に問題があるのかが一目瞭然となります。
しかし、中堅規模以上の企業であっても、これらの複雑な計算をExcelや部門ごとに散在したシステムで行っているケースが少なくありません。手作業による集計は時間がかかる上にミスも起きやすく、経営層が数字を確認できる頃にはすでに状況が変わっているということもあり得ます。独立採算制の効果を最大化するためには、正確かつ迅速な経営判断を行うためのデータ基盤を整備し、部門別の損益状況をリアルタイムに可視化できる環境を整えることが推奨されます。
独立採算制を導入する3つのメリット
独立採算制の導入は、単に部門ごとの収支を明確にするだけでなく、組織全体の競争力を高めるための強力なドライバーとなります。企業規模が拡大し、年商100億円を超えるような中堅企業へと成長する過程では、トップダウン型の経営だけでは現場の細かな変化に対応しきれなくなるケースが少なくありません。
ここでは、独立採算制がもたらす主な3つのメリットについて解説します。
経営者意識を持つ次世代リーダーの育成
最大のメリットは、将来の経営幹部候補となる人材の育成です。独立採算制では、各部門を一つの「会社」と見なし、部門長に大幅な権限と責任を委譲します。これにより、部門長は単に与えられた業務を遂行するだけでなく、自部門の損益(P/L)に責任を持つことになります。
自ら売上目標を立て、経費をコントロールし、利益を創出するプロセスを経験することで、部門長は自然と「経営者感覚」を身につけていきます。次世代を担うリーダーが、実践を通じて経営の勘所を養える環境を作れることは、企業の永続的な成長において極めて重要な要素です。
迅速な意思決定と現場のモチベーション向上
権限委譲が進むことで、意思決定のスピードが格段に向上します。従来のピラミッド型組織では、現場の稟議が経営層に承認されるまでに時間がかかり、ビジネスチャンスを逃してしまうことがありました。独立採算制では、現場に近いリーダーが即座に判断を下せるため、市場の変化や顧客の要望に対して柔軟かつスピーディーに対応できます。
また、自分たちの頑張りがダイレクトに部門の業績として数値化されるため、現場社員のモチベーション向上にもつながります。成果が可視化されることで、組織内に健全な競争意識と達成感が生まれます。
- 現場リーダーによる即断即決が可能になり、機会損失を防げる
- 成果と報酬や評価が連動しやすくなり、社員の士気が高まる
- 自分たちの部門経営に参加しているという当事者意識が醸成される
収益構造の可視化とコスト意識の浸透
3つ目のメリットは、社内の収益構造が透明化されることです。全社一括の会計では埋もれてしまいがちな「どの事業が利益を生み、どの事業が足を引っ張っているか」という実態が、部門別損益計算書によって白日の下に晒されます。
これにより、不採算部門の早期発見と対策が可能になるだけでなく、現場の一人ひとりにコスト意識が浸透します。「経費を使えば利益が減る」という当たり前の事実を、自分たちの部門の数字として実感できるからです。
| 比較項目 | 従来の機能別組織 | 独立採算制組織 |
|---|---|---|
| 損益責任の所在 | 曖昧になりがち(経営層のみ) | 明確(各部門長) |
| コスト意識 | 予算消化型になりやすい | 利益創出のために経費を最小化する意識が働く |
| 経営情報の粒度 | 全社単位で大枠を把握 | 部門・製品単位で詳細に把握 |
ただし、これらのメリットを享受するためには、正確なデータをタイムリーに収集・集計できる仕組みが不可欠です。Excelや個別のシステムが乱立している状態では、正しい部門別損益を算出するだけで膨大な工数がかかってしまいます。独立採算制の効果を最大化するためには、経営基盤となるシステムの整備も視野に入れる必要があるでしょう。
独立採算制のデメリットと注意点
独立採算制は、部門ごとの収益性を高め、次世代のリーダーを育成する上で非常に強力な経営手法です。しかし、その仕組みの性質上、運用方法を誤ると組織全体に深刻な弊害をもたらすリスクも潜んでいます。
特に、事業規模が拡大し、部門間の連携が複雑化している中堅企業においては、制度の負の側面が顕在化しやすくなります。ここでは、独立採算制を導入・運用する際に必ず押さえておくべきデメリットと、その対策について解説します。
セクショナリズムによる全社最適の阻害
独立採算制における最大の懸念点は、部門間の壁が高くなる「セクショナリズム(割拠主義)」の発生です。各部門が自部門の利益目標達成を最優先するあまり、会社全体の利益(全社最適)を損なう行動をとってしまう現象です。
例えば、ある部門が保有している顧客情報を、将来的な競合を恐れて他部門に共有しなかったり、全社的なプロジェクトへの人的リソースの拠出を拒んだりするケースが挙げられます。これは、「部分最適」が「全体最適」を阻害している典型的な状態です。
- 自部門の利益確保を優先し、他部門への協力やノウハウ共有を拒否する
- 部門間での顧客の奪い合いや、重複した営業活動による顧客満足度の低下
- 全社共通の課題解決よりも、自部門の短期的な数値達成にリソースが割かれる
こうした事態を防ぐためには、評価制度において「部門利益」だけでなく、「他部門への貢献度」や「全社利益への寄与」を組み込むことが重要です。また、経営層が常に全社視点でのメッセージを発信し続ける必要があります。
短期的な利益追求への偏りと対策
独立採算制では、部門ごとの期間損益が厳格に管理されます。これにより、部門責任者はどうしても「今期の数字」を作ることに意識が集中しがちになります。
その結果、将来の成長に必要な投資(人材育成、研究開発、設備投資、ブランド構築など)をコストと見なし、削減してしまう「縮小均衡」に陥るリスクがあります。短期的なP/L(損益計算書)は良くなっても、長期的には競争力を失うことになりかねません。
短期志向による弊害の具体例は以下の通りです。
| 削減されやすい項目 | 短期的な影響 | 長期的な弊害(リスク) |
|---|---|---|
| 教育研修費 | 経費削減による利益増 | 次世代人材が育たず、組織力が低下する |
| 研究開発費 | コストダウン | 新商品・新技術が生まれず、市場競争力を失う |
| マーケティング費 | 販管費の抑制 | ブランド認知が低下し、将来の売上基盤が弱まる |
この問題への対策としては、単なる財務指標だけでなく、顧客満足度やプロセス改善、人材育成状況などを評価する「バランスト・スコアカード(BSC)」のような多面的な評価軸を導入することが有効です。
管理会計業務の複雑化と負担増大
独立採算制を精緻に運用しようとすればするほど、経理部門や各部門の管理者の事務負担は増大します。これは、財務会計とは異なる「管理会計」独自のルール設計と運用が必要になるためです。
特に、本社費用の配賦計算(共通費の割り振り)や、部門間でやり取りされる製品・サービスの価格設定(社内振替価格)は、公平性を保つために複雑な計算を要します。多くの中堅企業では、これらの計算をExcelなどの表計算ソフトで行っていますが、組織変更や事業拡大のたびにメンテナンスが必要となり、業務が属人化しやすい傾向にあります。
- 配賦基準の変更に伴う、膨大なExcelファイルの修正作業
- 部門間のデータ連携が手作業で行われることによる、転記ミスや数値の不整合
- 月次決算の確定が遅れ、経営判断に必要な情報の鮮度が落ちる
- 各部門が独自のフォーマットで管理を行い、全社での数値統合が困難になる
正確かつ迅速な部門別損益管理を行うためには、手作業や分散したシステムでの運用には限界があります。独立採算制のメリットを享受しつつ、管理コストを最小化するためには、データを一元管理できる基盤の整備が不可欠です。
独立採算制と他の組織形態との違い
独立採算制の導入を検討する際、よく比較されるのが「カンパニー制」や「事業部制」といった組織形態です。しかし、これらは必ずしも対立する概念ではなく、独立採算制という管理手法をどのレベルの組織単位で、どの程度の権限委譲を伴って適用するかという「深さ」や「範囲」の違いとして理解する必要があります。
組織の成長フェーズや抱える課題によって最適な形態は異なります。ここでは、それぞれの特徴と違いを整理し、自社に適した運用を見極めるための視点を解説します。
カンパニー制と独立採算制の違い
カンパニー制とは、事業部門をあたかも一つの独立した会社(カンパニー)のように見なし、大幅な権限委譲を行う組織形態です。独立採算制の考え方をさらに推し進め、より高度な自律性を求めた形態と言えます。
両者の最大の違いは、管理する経営数字の範囲と権限の大きさにあります。一般的な独立採算制(または事業部制)では、主に損益計算書(P/L)上の利益責任を負いますが、カンパニー制では貸借対照表(B/S)を含めた責任を持つことが一般的です。つまり、利益だけでなく、資産効率やキャッシュフローに対する責任まで負うことになります。
- 独立採算制(広義):部門ごとの収支を管理し、利益責任を明確にする仕組み。
- カンパニー制:擬似的な別会社として、人事権や投資権限、B/S管理まで委譲する組織形態。
以下の表は、独立採算制を採用した一般的な事業部と、カンパニー制の違いを比較したものです。
| 比較項目 | 一般的な独立採算制(事業部) | カンパニー制 |
|---|---|---|
| 責任範囲 | 主に売上・利益(P/L) | 利益に加え、資産・資金(B/S・CF) |
| 権限委譲 | 業務執行権限が中心 | 人事権、投資権限、研究開発など包括的 |
| 意思決定 | 本社承認が必要な事項が多い | カンパニー長に大幅に委譲され迅速 |
| 組織の独立性 | 本社機能(人事・経理等)に依存 | 独自の管理部門を持つ場合が多い |
カンパニー制は、経営者人材の育成や意思決定の迅速化において強力な効果を発揮しますが、組織の重複によるコスト増加や、全社的なガバナンスが効きにくくなるといったリスクも孕んでいます。ERPなどを活用して全社の経営データをリアルタイムに統合管理できる基盤がなければ、各カンパニーの状況がブラックボックス化してしまう恐れがあるため注意が必要です。
事業部制と独立採算制の違い
事業部制は、製品、地域、顧客などの単位で組織を分割し、各事業部が利益責任を持つ組織形態です。日本の中堅・大企業において最も広く普及している形態であり、独立採算制を具現化するための「器」として機能します。
「事業部制」と「独立採算制」は違いというよりも、包含関係にあります。事業部制組織において、その採算管理を徹底するための手法が独立採算制です。ただし、組織図上は事業部制を敷いていても、実態としては権限委譲が進んでおらず、単なる売上集計単位になっているケースも少なくありません。
真の意味での独立採算制を事業部制の中で機能させるためには、以下の点が重要になります。
- 本社費(共通費)の配賦ルールを明確にし、事業部の純粋な貢献利益を可視化すること
- 事業部長に対して、目標達成のための予算執行権限を適切に与えること
- 社内振替価格を設定し、部門間の取引を市場原理に基づいて評価すること
事業部制において独立採算を厳格に適用しようとすると、部門間での利益の奪い合いや、セクショナリズムが発生しやすくなります。これを防ぐためには、単に部門ごとの数字を競わせるだけでなく、全社利益への貢献度を評価する仕組みや、データの透明性を担保するシステム環境が不可欠です。
Excelや個別の会計システムが乱立している状態では、配賦計算や内部取引の消去に膨大な工数がかかり、迅速なフィードバックができません。正確な部門別損益をタイムリーに把握できる環境を整えることが、制度運用の成功鍵となります。
独立採算制の導入を成功させるポイント
独立採算制は、部門ごとの収益責任を明確にし、社員の経営者意識を醸成するための強力なフレームワークです。しかし、単に制度を導入するだけでは、組織の分断や不公平感といった副作用を招くリスクがあります。
制度を機能させ、全社的な利益最大化につなげるためには、運用の「ルール設計」と「インフラ整備」が鍵を握ります。ここでは、導入を成功に導くために不可欠な3つのポイントを解説します。
公平で納得感のある社内振替価格の設定
独立採算制において最も対立が起きやすいのが、部門間での取引価格である「社内振替価格(移転価格)」の設定です。例えば、製造部門が営業部門に製品を渡す際の価格が高すぎれば、製造部門の利益は出やすくなりますが、営業部門は利益を出しにくくなります。
この価格設定に客観的な妥当性がない場合、部門間で不毛な価格交渉が発生し、本来の目的である「市場での競争力強化」がおろそかになりかねません。納得感を醸成するためには、以下のいずれかの基準をベースに、自社の業態に合わせたルールを策定する必要があります。
- 市価基準法:市場価格をベースにする方法。客観性が高いが、市場に類似製品がない場合は適用が難しい。
- 原価基準法:製造原価に一定の利益(マークアップ)を上乗せする方法。計算は容易だが、コスト削減へのインセンティブが働きにくい場合がある。
- 折衝価格法:部門間の話し合いで決定する方法。納得感は得やすいが、交渉に多大な時間と労力を要するリスクがある。
重要なのは、一度決めたルールを固定化せず、市場環境の変化に応じて定期的に見直す運用体制を整えることです。
共通費の配賦ルールの明確化
本社部門(人事、総務、経理、情報システムなど)にかかるコスト、いわゆる「共通費」を、各事業部門にどのように負担させるか(配賦するか)も重要な論点です。
「なぜ自分たちの部門がこれほどの本社費を負担しなければならないのか」という不満が現場から出始めると、独立採算制へのモチベーションは著しく低下します。これを防ぐためには、ブラックボックス化しやすい配賦計算を透明化し、因果関係に基づいた「配賦基準(ロジック)」を明確にする必要があります。
以下は、一般的な配賦基準の例です。
| 共通費の費目 | 推奨される配賦基準の例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 本社家賃・施設維持費 | 占有床面積 | 使用しているスペースに応じて負担する |
| 人事・総務費 | 従業員数 | サービスを受ける人数に応じて負担する |
| 情報システム費 | PC台数・ID数 | 利用しているITリソース量に応じて負担する |
| 経営企画・役員報酬 | 売上高・売上総利益 | 事業規模(負担能力)に応じて負担する |
配賦ルールを明確にすることで、各部門は「どうすれば自部門が負担するコストを下げられるか」を考えるようになります。例えば、無駄なスペースを返上したり、ITリソースを適正化したりといった、全社的なコスト削減意識へとつながります。
リアルタイムな経営数字の把握
独立採算制の肝は、現場のリーダーが「経営者」として自律的に意思決定を行う点にあります。しかし、その判断材料となる部門別損益計算書(P/L)が、翌月末の月次決算を待たなければ出てこないようでは、迅速な手は打てません。
市場の変化が激しい現代において、1ヶ月前の数字を見て対策を練るのでは遅すぎます。日次、あるいは週次で概算損益が把握できる環境があって初めて、現場は「今月の目標達成のために、今日何をすべきか」を具体的に行動へ移すことができます。
多くの企業では、部門ごとのデータをExcelで集計・加工しているためにタイムラグが発生していますが、システム基盤を整え、経営数字をリアルタイムに可視化することこそが、独立採算制を形骸化させないための必須条件です。正確かつ迅速なデータがあってこそ、権限委譲は真の効力を発揮します。
独立採算制の効果を最大化するERPの活用
独立採算制を導入し、組織の末端まで採算意識を浸透させるためには、正確かつタイムリーな経営情報の把握が不可欠です。しかし、多くの中堅企業では、部門ごとの損益計算をExcelや個別の業務システムに依存しており、集計作業に膨大な工数を要しているのが実情ではないでしょうか。
独立採算制の運用を成功させ、経営のスピードを加速させるためには、統合基幹業務システム(ERP)の活用が極めて有効な手段となります。本章では、ERPがどのように独立採算制の課題を解決し、その効果を最大化するのかについて解説します。
部門別データの統合管理と見える化
独立採算制において最も重要なのは、各部門長が自部門の収益状況をリアルタイムに把握し、迅速なアクションを起こせる環境を作ることです。従来のアナログな管理手法や、販売・会計・人事が分断されたシステム環境では、月次決算が締まるまで部門の正確な数字が見えず、対策が後手に回るリスクがあります。
ERPを導入することで、受注、売上、購買、在庫、経費といったあらゆる業務データが一つのデータベースに統合されます。これにより、部門ごとの損益情報が日次レベルで可視化され、経営層や部門責任者はいつでも最新の数字に基づいた意思決定が可能になります。
- データ入力の二度手間をなくし、転記ミスやデータの不整合を防ぐ
- ドリルダウン機能により、損益の悪化原因を伝票レベルまで即座に追跡できる
- 予実管理(予算と実績の比較)をリアルタイムに行い、早期の軌道修正を可能にする
このようにデータを統合管理することで、現場の数字に対する信頼性が高まり、部門長は集計作業ではなく、業績改善のための戦略立案に時間を割けるようになります。
複雑な会計処理の自動化と業務効率化
独立採算制を厳密に運用しようとすると、社内振替価格の計算や、本社共通費(家賃、光熱費、管理部門の人件費など)の各部門への配賦計算が複雑化します。これらをExcelで行っている場合、計算ロジックがブラックボックス化したり、組織変更のたびにマクロの修正が必要になったりと、経理部門に多大な負荷がかかります。
ERPの管理会計機能を活用すれば、あらかじめ設定したルールに基づいて、これらの複雑な計算を自動化することが可能です。以下の表は、独立採算制の運用における従来型の手法とERP活用時の比較です。
| 比較項目 | Excel・個別システムによる管理 | ERPによる統合管理 |
|---|---|---|
| 配賦計算 | 手作業による集計・計算が必要で、ミスが発生しやすい。計算根拠が不明確になりがち。 | 売上比、人員比、面積比などの基準に基づき自動配賦。計算プロセスが透明化される。 |
| 社内振替 | 部門間の取引を手動で調整する必要があり、照合に時間がかかる。 | 部門間取引の入力と同時に、社内売上・社内仕入が自動仕訳され、相殺消去もスムーズ。 |
| 組織変更への対応 | 計算シートの作り直しや過去データの組み替えに多大な工数がかかる。 | マスタ設定の変更のみで、新組織体制に合わせた集計や過去データの遡及シミュレーションが容易。 |
このように定型業務を自動化することで、月次決算の早期化が実現します。結果として、経営層は前月の確定数値をより早いタイミングで確認でき、次の一手を素早く打つことができるようになります。
全社最適を実現する経営基盤の構築
独立採算制のデメリットとして懸念される「セクショナリズム(部分最適)」を防ぐためにも、ERPは重要な役割を果たします。各部門が自部門の利益のみを追求するあまり、会社全体の利益を損なうような行動をとっていないか、経営層が監視・監督する必要があります。
ERPによって構築された経営基盤では、部門ごとのPL(損益計算書)だけでなく、部門別BS(貸借対照表)やキャッシュフローの管理も可能になります。これにより、単なる売上・利益の追求だけでなく、在庫回転率やROIC(投下資本利益率)といった指標を用いて、投資効率やキャッシュフローを意識した経営評価を行うことができます。
- 部門間のシナジー効果や、全社視点でのリソース配分の最適化を支援する
- 共通の数値基準(モノサシ)を持つことで、部門間の公平な評価と納得感を醸成する
- 在庫の滞留や債権回収の遅れなど、PLには表れにくい経営リスクを早期に検知する
ERPは単なる業務効率化ツールではなく、独立採算制の運用を支え、部分最適の弊害を乗り越えて全社最適を実現するための「経営の羅針盤」となるのです。
独立採算制に関するよくある質問
独立採算制とアメーバ経営にはどのような違いがありますか?
アメーバ経営は京セラの名誉会長である稲盛和夫氏が考案した経営手法であり、独立採算制を小集団(アメーバ)単位まで細分化して徹底したものです。つまり、独立採算制という大きな枠組みの中に、具体的な運用手法の一つとしてアメーバ経営が含まれるという関係性になります。
中小企業でも独立採算制を導入することは可能ですか?
可能です。企業規模にかかわらず、部門や店舗ごとの収支を明確に管理することで、社員の当事者意識を高める効果が期待できます。ただし、導入には部門別損益計算書を作成できる管理会計の仕組みを整える必要があります。
独立採算制の導入で起こりやすい失敗には何がありますか?
自部門の利益を優先するあまり、他部門との協力体制が崩れるセクショナリズムが挙げられます。また、短期的な利益目標の達成に固執し、人材育成や設備投資といった長期的な視点が欠落してしまうケースも少なくありません。
社内振替価格はどのように設定するのが適切ですか?
市場価格を基準とする市価基準法や、製造原価に一定の利益を加算する原価基準法などが一般的です。重要なのは計算方法そのものよりも、売り手部門と買い手部門の双方が納得できる公平なルールを事前に定めておくことです。
独立採算制における共通費の配賦基準はどう決めるべきですか?
本社機能などの共通費は、売上高、人員数、使用面積などの比率に基づいて各部門へ配賦します。どの基準を採用する場合でも、なぜその基準なのかという根拠を明確にし、現場の不公平感を解消しておくことが運用のポイントです。
まとめ
独立採算制は、次世代リーダーの育成や現場のコスト意識向上に大きく寄与する有効な経営手法です。一方で、セクショナリズムの弊害や短期的な利益追求への偏りといった課題も存在します。これらのデメリットを解消し、制度導入を成功に導くためには、公平な社内ルールの策定と、リアルタイムな経営数字の把握が不可欠です。
特に、部門別の損益を正確かつ迅速に可視化するには、表計算ソフトなどを用いた手作業での集計には限界があります。全社的なデータを統合管理し、意思決定のスピードを加速させるためには、ERP(統合基幹業務システム)の活用が極めて有効です。組織の全体最適を実現するために、まずは自社に適したERPの情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。