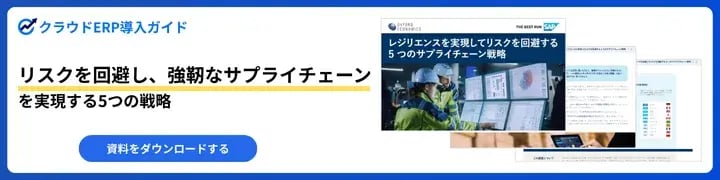「適正在庫を維持しているはずが、気づけば倉庫に商品が溢れている」「売れ残った在庫の管理コストが経営を圧迫している」など、多くの企業が余剰在庫の問題に直面しているのではないでしょうか。余剰在庫は、単に保管スペースを無駄にするだけでなく、キャッシュフローの悪化や商品価値の低下を招き、企業の収益性を著しく損なうサイレントキラーです。しかし、なぜ対策を講じているにもかかわらず、余剰在庫は発生し続けてしまうのでしょうか。
本記事では、余剰在庫が経営に与える具体的な影響から、その根本的な5つの原因、そして明日からでも実践できる7つの削減・防止策までを、企業の在庫管理担当者様向けに網羅的に解説します。結論から言えば、余剰在庫問題の根本解決には、部門間の壁を越えた情報連携と、それに基づいた精度の高い需要予測が不可欠です。この記事を最後までお読みいただくことで、貴社の在庫最適化と収益改善に向けた具体的な道筋が見えるはずです。
この記事で分かること
- 余剰在庫がキャッシュフローや利益を圧迫する具体的な理由
- 需要予測のズレや部門間の連携不足といった発生の5大原因
- 在庫の可視化から販売戦略まで、今すぐできる7つの削減・防止策
- 根本解決に繋がる在庫管理システムやERPの重要性
余剰在庫が経営を圧迫する3つの理由
余剰在庫は、単に「売れ残ったモノ」という問題に留まりません。それは企業の財務体質を静かに蝕み、成長の足枷となる経営上の重大な課題です。特に、キャッシュフローの悪化、管理コストの増大、そして商品価値の低下という3つの側面から、経営に深刻なダメージを与えます。ここでは、それぞれがどのように経営を圧迫するのかを具体的に解説します。
理由1:キャッシュフローの悪化と資金繰りの圧迫
会計上、在庫は「棚卸資産」として貸借対照表に計上されます。しかし、これは現金化されて初めて企業の利益となるものであり、在庫として保管されている間は、仕入れや製造に投じた資金が固定化されている状態に他なりません。 余剰在庫が増えれば増えるほど、企業の自由に使える現金(フリーキャッシュフロー)は減少し、運転資金を圧迫します。
この状態が続くと、黒字であるにもかかわらず資金がショートする「黒字倒産」のリスクを高めることになります。 帳簿上は利益が出ていても、支払いに必要な現金が手元になければ、仕入先への支払いや従業員の給与、借入金の返済などが滞り、事業継続が困難になるのです。 健全な企業経営において、キャッシュフローの維持は生命線であり、余剰在庫はその流れを滞らせる最大の要因の一つと言えるでしょう。
理由2:保管・管理コストの継続的な発生
在庫は、ただ保管しておくだけでも様々なコストが発生し続けます。 これらのコストは、一つひとつは小さく見えても、積み重なると利益を大きく削り取る要因となります。在庫を保有することで発生する主なコストは以下の通りです。
| コストの種類 | 内容 |
|---|---|
| 保管費用 | 倉庫の賃料、光熱費、保険料、固定資産税など、在庫を物理的に保管するためにかかる費用。 |
| 人件費 | 在庫の入出庫、棚卸、検品、管理システムへの入力など、在庫管理に関わる従業員への給与や手当。 |
| 設備費用 | 商品を保管するための棚やラック、運搬用のフォークリフト、在庫管理システムやハンディターミナルなどの導入・維持費用。 |
| 在庫金利 | 在庫を仕入れるために金融機関から借り入れを行った場合に発生する金利。在庫として資金が固定化されている期間中、支払い続ける必要がある。 |
これらの「見えにくいコスト」は、余剰在庫の量に比例して増大します。 在庫を圧縮することは、これらの継続的な支出を削減し、企業の収益構造を改善するために不可欠です。
理由3:商品価値の低下による評価損と廃棄ロス
在庫として保管されている商品は、時間の経過とともにその価値が低下するリスクに常に晒されています。 特に、製品ライフサイクルが短い現代においては、「陳腐化」による価値の低下は深刻な問題です。 具体的には、以下のような要因で商品価値は失われていきます。
- 物理的な劣化:保管中の破損、汚れ、品質の低下など。
- 流行の変化:アパレル製品やデザイン性の高い雑貨など、トレンドが過ぎることで市場価値がなくなる。
- 技術革新:新しいモデルや後継機が登場することで、旧モデル(型落ち品)の価値が著しく低下する。
- 季節性:季節限定商品がシーズンを過ぎて売れ残る。
このように価値が著しく低下した在庫は、会計処理上「棚卸資産評価損」として損失計上する必要があります。 これは企業の利益を直接的に押し下げる要因となります。さらに、販売が見込めないと判断された在庫は、最終的に廃棄処分せざるを得ません。 廃棄には処分費用がかかるだけでなく、仕入れや製造にかけたコストが全て損失となり、企業の収益に大きな打撃を与えるのです。
余剰在庫はなぜ発生するのか 5つの主な原因
余剰在庫は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。問題を根本的に解決するためには、まず自社がどの原因に当てはまるのかを正確に把握することが不可欠です。ここでは、多くの企業で共通してみられる5つの主な原因を掘り下げて解説します。
原因1 需要予測の精度が低い
余剰在庫が発生する最も直接的な原因の一つが、需要予測の精度の低さです。将来の製品需要を正確に予測できなければ、生産計画や仕入れ計画も実需と乖離し、結果として在庫の過不足が生じます。特に、以下のような状況は需要予測の精度を著しく低下させます。
- 担当者の経験や勘への依存: 過去の実績や担当者の個人的な感覚に頼った予測は、属人化しやすく客観性に欠けます。市場環境の変化や担当者の交代によって、予測精度が大きく揺らぐリスクを常に抱えています。
- 過去の販売実績のみを基準とした予測: 過去のデータは重要な指標ですが、それだけでは市場の新たなトレンド、競合の動向、季節変動といった未来の要素を捉えきれません。特に、市場の変化が激しい製品においては、過去の成功体験が未来の失敗要因となることも少なくありません。
- 市場や顧客データの分析不足: 新規顧客の動向、プロモーション活動への反応、Webサイトのアクセスデータといった、販売実績以外の多様なデータを活用できていない場合、需要の兆候を見逃しやすくなります。
これらの要因が重なることで、予測と実需の間に大きなギャップが生まれ、その結果として売れ残りの在庫、すなわち余剰在庫が積み上がっていくのです。
原因2 部門間の情報連携が不足している
企業の成長に伴い、営業、マーケティング、生産、購買といった部門が専門化・細分化される一方で、部門間の壁が生まれてしまうことがあります。この部門間の情報連携不足は、余剰在庫を生み出す深刻な原因となります。
各部門はそれぞれのミッションやKPI(重要業績評価指標)を持っており、その達成を最優先に行動しがちです。例えば、営業部門は欠品による機会損失を避けるために多めの在庫を求め、生産部門は生産効率を上げるために計画通りの生産量を維持しようとします。しかし、それぞれの部門が持つ情報がリアルタイムで共有されていなければ、お互いの状況を考慮しない「部門最適」の意思決定が横行し、全社的には過剰な在庫を抱えるという矛盾した状況に陥ります。
| 部門 | 保有する重要な情報(一例) | 情報連携不足による問題 |
|---|---|---|
| 営業部門 | ・最新の受注見込み ・大型案件の進捗状況 ・顧客からのフィードバック |
見込み情報が生産計画に反映されず、急な大口受注に対応できない、または失注したにもかかわらず生産が進んでしまう。 |
| マーケティング部門 | ・販売促進キャンペーンの計画 ・メディアへの露出予定 ・市場トレンド分析 |
キャンペーンによる需要増が在庫計画に織り込まれず、欠品による販売機会の損失と顧客満足度の低下を招く。 |
| 生産・購買部門 | ・生産ラインの稼働状況 ・原材料の納期 ・サプライヤーの動向 |
生産の遅延や原材料の納期遅れといった情報が営業部門に伝わらず、顧客への納期回答が不正確になり、信頼を損なう。 |
このように、各部門が持つ情報がサイロ化(分断)されることで、サプライチェーン全体で歪みが生じ、その結果が余剰在庫として現れるのです。
原因3 過剰な生産計画や仕入れ
需要予測のズレや部門間の連携不足とも関連しますが、「欠品」に対する過度な恐怖心から、意図的に過剰な生産計画や仕入れを行ってしまうケースも少なくありません。欠品は販売機会の損失に直結するため、それを避けたいという心理が働くのは自然なことです。しかし、その結果として安全在庫を必要以上に積み増してしまうと、キャッシュフローの悪化や保管コストの増大といった形で経営を圧迫します。
また、仕入れ単価を下げるために一度に大量発注を行ったり、生産効率を優先して最低生産ロット数を多く設定したりすることも、結果的に余剰在庫を生む一因となります。目先のコスト削減や効率化が、長期的には在庫コストという大きな負担となって跳ね返ってくる可能性があることを認識する必要があります。
原因4 リードタイムの長さと不確実性
リードタイムとは、製品の発注から納品までに要する時間のことです。このリードタイムが長ければ長いほど、その期間中に発生する需要変動のリスクが高まり、需要予測はより困難になります。
例えば、原材料を海外から調達している場合、輸送に数ヶ月を要することも珍しくありません。その数ヶ月の間に市場環境が急変し、需要が大きく落ち込んでしまうと、製品が完成する頃にはすでに大量の余剰在庫となってしまいます。欠品を避けるためには、この長いリードタイムを見越して、より多くの在庫を抱えざるを得なくなります。
さらに、リードタイムの「不確実性」も問題です。サプライヤーの生産トラブル、輸送中の事故、通関の遅れ、昨今の世界情勢の変化など、リードタイムを変動させる要因は数多く存在します。こうした不確実性に対応するため、企業はさらに多くのバッファ(余裕)在庫を持つことになり、余剰在庫のリスクを高めてしまうのです。
原因5 製品ライフサイクルの短期化
現代の市場は、顧客ニーズの多様化や技術革新の加速により、製品のライフサイクルが著しく短くなっています。次々と新製品が投入され、既存製品はあっという間に陳腐化してしまう時代です。
特に、エレクトロニクス業界やアパレル業界など、トレンドの変化が激しい分野ではこの傾向が顕著です。ライフサイクルの終盤にある製品の需要を正確に見極め、生産や仕入れを適切に縮小していかなければ、モデルチェンジやシーズンの終わりとともに、旧製品は一気に不良在庫と化してしまいます。
市場投入から成熟期、衰退期に至るまでの各段階で、販売計画と在庫計画を柔軟に見直し、需要の減速に合わせて速やかに在庫を削減していく高度な管理体制が求められます。この変化のスピードに対応できないことが、余剰在庫の発生に直結するのです。
関連記事はこちら
今すぐできる余剰在庫の削減・防止策7選
余剰在庫は、気付かぬうちに経営資源を圧迫する深刻な問題です。しかし、適切な対策を講じることで、そのリスクを大幅に軽減することが可能です。ここでは、多くの企業がすぐに着手できる7つの具体的な削減・防止策を、優先順位の高いものから順に解説します。
対策1 在庫状況の可visible化とABC分析
余剰在庫対策の第一歩は、自社の在庫状況を正確に把握することから始まります。どこに、何が、どれだけあるのかをリアルタイムで把握できなければ、的確な対策は打てません。まずは、散在する在庫情報を一元管理し、全社で共有できる仕組みを構築することが不可欠です。
現状を把握した上で、次に行うべきが「ABC分析」です。 ABC分析とは、在庫を重要度に応じてA・B・Cの3つのランクに分類し、管理の優先順位を明確にする手法です。 一般的には、売上高の高い順に商品を並べ、その累計構成比によってランク分けを行います。
| ランク | 売上構成比(目安) | 品目数構成比(目安) | 管理方針 |
|---|---|---|---|
| Aランク | 〜80% | 〜20% | 最重要在庫 欠品を絶対に避け、在庫精度を常に高く維持する。発注方式や需要予測を重点的に管理する。 |
| Bランク | 80%〜95% | 〜30% | 中程度重要在庫 Aランクに準じた管理を行うが、ある程度の安全在庫を許容し、管理コストとのバランスを取る。 |
| Cランク | 95%〜100% | 〜50% | 低重要度在庫 管理コストを極力かけない。定期発注方式などで発注の手間を省き、在庫削減の主要ターゲットとする。 |
このように在庫をランク分けすることで、管理すべき重要な在庫(Aランク)と、積極的に削減すべき在庫(Cランク)が明確になります。リソースをAランクの在庫管理に集中させることで、欠品による機会損失を防ぎつつ、Cランクの在庫を圧縮することでキャッシュフローの改善が期待できます。
対策2 適正な需要予測モデルの構築
需要予測の精度の低さは、余剰在庫発生の根本的な原因の一つです。 担当者の経験や勘だけに頼った発注は、過剰在庫のリスクを常に伴います。精度の高い需要予測を行うためには、過去の販売実績データに加え、季節変動、市場トレンド、競合の動向、販売促進計画といった多様な要因を考慮する必要があります。
需要予測の手法には、移動平均法や指数平滑法といった統計的手法から、AIを活用した高度な予測まで様々です。 まずは過去のデータを用いて複数の予測手法を試し、自社の製品特性に最も合ったモデルを見つけることが重要です。 定期的に予測と実績の乖離を分析し、予測モデルを継続的に改善していくPDCAサイクルを回すことが精度向上に繋がります。
対策3 リードタイムの短縮と最適化
発注してから商品が納品されるまでの期間(リードタイム)が長ければ長いほど、その間の需要変動リスクに備えるために多くの「安全在庫」を抱える必要が生じます。 このリードタイムは、以下の3つに分解できます。
- 発注リードタイム:発注業務にかかる時間
- 製造リードタイム:製品の生産にかかる時間
- 調達・配送リードタイム:サプライヤーからの納品や顧客への配送にかかる時間
これらの各工程を見直し、ボトルネックとなっている部分を特定・改善することで、全体のリードタイムは短縮可能です。 例えば、サプライヤーとの連携を強化して納品サイクルを短縮したり、社内の発注承認プロセスをデジタル化したりするだけでも効果が期待できます。リードタイムの短縮は、安全在庫の削減に直結し、キャッシュフローを大きく改善させる効果があります。
対策4 定期的な販売計画と在庫計画の見直し
市場環境や顧客ニーズは絶えず変化しています。一度策定した販売計画や在庫計画が、数ヶ月後には陳腐化している可能性も少なくありません。こうした変化に迅速に対応するためには、計画を定期的に見直す仕組みが不可欠です。
ここで重要になるのが、S&OP(Sales & Operations Planning)という考え方です。 S&OPとは、販売部門と生産・調達・在庫管理部門が連携し、需要と供給の情報を共有しながら、事業計画の達成に向けて意思決定を行うプロセスのことです。 月次などのサイクルで各部門が集まり、販売実績と予測の差異分析、市場の変化などを踏まえて、販売計画と在庫計画を修正していきます。 これにより、部門間の連携が強化され、全社最適の視点での在庫コントロールが可能になります。
対策5 返品ルールの厳格化
特にBtoB取引において、安易な返品の受け入れは余剰在庫の温床となり得ます。返品された商品は、検品や再梱包のコストがかかるだけでなく、品質が劣化して再販できず、そのまま不良在庫となるケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐため、取引開始時に契約書で返品条件(返品可能な期間、商品の状態、送料負担など)を明確に定めておくことが重要です。もちろん、顧客との良好な関係を維持することも大切ですが、明確なルールを設けることで、無用な返品を抑制し、在庫リスクを低減させることができます。
対策6 在庫のセールやアウトレットでの販売
ここまでの対策は「防止策」ですが、すでに発生してしまった余剰在庫に対しては、迅速に現金化する「削減策」を講じる必要があります。 在庫を長期間保有し続けると、保管コストがかさむだけでなく、品質劣化により最終的に廃棄せざるを得なくなるリスクが高まります。
具体的な処分方法としては、以下のような選択肢が考えられます。
- 自社でのセール販売:ECサイトや実店舗でセールを実施し、早期の販売を目指す。
- アウトレットでの販売:ブランドイメージを維持しつつ、正規の販路とは別に販売する。
- 在庫買取業者への売却:専門業者に一括で買い取ってもらうことで、迅速に現金化し、保管スペースを確保する。
ただし、セールによる値引き販売はブランドイメージの低下につながる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。 これらの方法はあくまで対症療法であり、なぜ余剰在庫が発生したのかという根本原因の解決にはならない点を理解しておく必要があります。
対策7 在庫管理システムの導入検討
これまで挙げてきた6つの対策を、Excelや手作業だけで実行・管理するには限界があります。特に、拠点や取り扱い品目が増えるほど、情報の集計や分析に膨大な工数がかかり、リアルタイムな状況把握は困難になります。
そこで有効なのが、在庫管理システムの導入です。在庫管理システムや、販売・会計など基幹業務全体を統合管理するERP(Enterprise Resource Planning)を導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 在庫状況のリアルタイムな可視化:全社の在庫情報を一元管理し、いつでも正確な状況を把握できる。
- 分析業務の効率化:ABC分析などの定型的な分析レポートを自動で作成できる。
- 需要予測精度の向上支援:蓄積されたデータを活用し、より客観的な需要予測が可能になる。
- 人的ミスの削減:手入力によるミスや発注漏れを防ぎ、業務の標準化を促進する。
システムの導入は、一時的にコストや労力がかかりますが、属人化していた在庫管理業務を標準化し、継続的に在庫を最適化していくための強固な基盤となります。Excel管理に限界を感じている、あるいは部門間の情報連携がうまくいっていないといった課題を抱えている企業にとって、システム化は根本的な解決策となり得るでしょう。
余剰在庫問題の根本解決には経営情報の統合が不可-欠
これまでの章でご紹介した7つの対策は、余剰在庫の削減・防止に有効な手段です。しかし、それらの多くは発生した問題への対症療法的な側面も持ち合わせています。余剰在庫という経営課題を根本から解決し、再発を防ぐためには、問題の根源にアプローチすることが不可欠です。その鍵となるのが、企業内に分散した経営情報の統合です。
多くの企業では、部門ごとにシステムが導入され、データが独立して管理されている「サイロ化」と呼ばれる状態に陥りがちです。 この情報の分断こそが、部門間の連携を妨げ、結果として余剰在庫を生み出す温床となっているのです。
部門最適の限界と全社最適の必要性
「部門最適」とは、各部門がそれぞれの目標達成や業務効率化を最優先する考え方です。 一見すると合理的ですが、組織全体で見たときに不利益を生むケースが少なくありません。余剰在庫の問題は、まさにこの部門最適の弊害が顕在化した典型例と言えるでしょう。
例えば、各部門が以下のような判断をした場合を考えてみましょう。
- 営業部門:「欠品による販売機会の損失は絶対に避けたい。少し多めに需要を予測しておこう」
- 製造部門:「生産計画を頻繁に変えると効率が落ちる。需要の変動を見越して、ある程度まとめて生産しておこう」
- 購買部門:「一度に大量に発注すれば、仕入れ単価を下げられる。コスト削減のために、多めに原材料を確保しておこう」
どの判断も、各部門の立場からすれば「最適」なものです。しかし、これらの「部分的な正解」が積み重なることで、企業全体としては「過剰な在庫」という大きな課題に行き着いてしまいます。 このように、部門最適の追求は、意図せずして在庫の積み増しを招き、キャッシュフローの悪化や保管コストの増大といった経営リスクを高めるのです。
この問題を解決するためには、個々の部門の視点ではなく、企業全体の視点から最適な状態を目指す「全社最適」への転換が不可欠です。 全社最適とは、各部門が持つ情報をリアルタイムで共有し、経営トップが全体を見渡した上で、最も合理的な意思決定を下せる状態を指します。
| 部門最適 | 全社最適 | |
|---|---|---|
| 視点 | 各部門のKPI達成が最優先 | 企業全体の利益最大化が最優先 |
| 情報共有 | 部門内に閉鎖的・限定的 | 部門横断でリアルタイムに共有 |
| 意思決定 | 部門長が個別に行う | 経営層が全社データに基づき行う |
| 結果 | 部門間の対立、余剰在庫や機会損失の発生 | 生産性の向上、キャッシュフローの改善 |
ERP導入で実現するリアルタイムな在庫管理
部門最適から全社最適へと舵を切る上で、強力な推進力となるのがERP(Enterprise Resource Planning:統合基幹業務システム)の導入です。 ERPは、販売、購買、生産、在庫、会計、人事といった企業の基幹業務を統合し、すべての情報を一つのデータベースで一元管理する仕組みです。
Excelや部門ごとに独立したシステムによる管理では、データの入力・転記に手間がかかるだけでなく、情報のタイムラグや入力ミスが発生しがちです。 これに対しERPを導入することで、企業活動のあらゆる情報がリアルタイムに連携・更新され、在庫状況を正確に可視化できるようになります。
例えば、営業部門が受注データを入力すれば、その情報は即座に在庫データに反映され、生産計画や購買計画にも自動で連携されます。 これにより、以下のような効果が期待できます。
- 精度の高い需要予測:全社の販売実績や受注情報を統合的に分析し、より正確な需要予測が可能になる。
- 在庫の適正化:リアルタイムの在庫情報に基づき、拠点間の在庫移動や生産調整を迅速に行えるため、欠品と過剰在庫を同時に抑制できる。
- キャッシュフローの改善:不要な在庫を圧縮することで、保管コストや廃棄ロスを削減し、運転資金をより有効に活用できる。
- 迅速な経営判断:経営層は、常に最新かつ正確な全社データに基づき、市場の変化に対応したスピーディーな意思決定を下せるようになる。
ERPは単なる在庫管理ツールではありません。点在する情報を有機的に結びつけ、企業の全体最適を実現するための経営基盤そのものです。余剰在庫という課題を根本的に解決し、持続的な成長を目指す上で、ERPによる経営情報の統合は極めて有効な一手となるでしょう。
余剰在庫に関するよくある質問
余剰在庫の処分にはどのような方法がありますか?
余剰在庫の処分方法には、セールやアウトレットでの販売、在庫買取業者への売却、海外への輸出、ECサイトでの販売、寄付、廃棄といった選択肢があります。製品の特性やブランドイメージを考慮して最適な方法を選ぶことが重要です。
余剰在庫は会計上、損金として計上できますか?
在庫を廃棄した場合、廃棄損として損金に計上できます。また、評価損を計上できるケースもありますが、災害による著しい損傷や著しい陳腐化など、税法上の厳格な要件を満たす必要があります。詳細は税理士などの専門家にご相談ください。
在庫管理システムを導入するメリットは何ですか?
在庫管理システムを導入するメリットは、在庫状況をリアルタイムで正確に把握できる点です。これにより、欠品や過剰在庫を防ぎ、発注業務の効率化や在庫回転率の向上、人的ミスの削減などが期待できます。
ABC分析とはどのような手法ですか?
ABC分析とは、在庫を重要度に応じてランク分けする管理手法です。売上高や利益への貢献度が高い順にA・B・Cの3グループに分類し、各グループの特性に合わせた管理を行うことで、在庫管理を効率化します。
適正在庫はどのように計算すればよいですか?
適正在庫の計算方法には、需要予測や安全在庫、発注サイクルなどを考慮した計算式を用いる方法や、在庫回転日数から算出する方法などがあります。業界や商材によって最適な計算方法は異なるため、自社の状況に合わせた手法を選択する必要があります。
まとめ
本記事では、余剰在庫が経営を圧迫する理由から、その主な発生原因、そして具体的な削減・防止策までを解説しました。余剰在庫は、需要予測の誤りや部門間の連携不足、不適切な生産・仕入れ計画など、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。その結果、保管コストの増大やキャッシュフローの悪化を招き、企業の収益性を著しく低下させる要因となります。
ご紹介した7つの対策は、余剰在庫の問題を改善するために有効な手段です。特に、在庫状況の可視化やABC分析による管理の徹底、需要予測精度の向上は、多くの企業ですぐに着手できる重要な取り組みです。これらの対策を一つひとつ実行することで、在庫の最適化に向けた大きな一歩を踏み出すことができるでしょう。
しかし、これらの個別施策だけでは、問題の根本的な解決には至らないケースも少なくありません。その背景には、販売、生産、購買といった各部門の情報が分断され、全社的な視点での意思決定ができていない「部門最適の壁」が存在します。この壁を乗り越え、余剰在庫問題を根本から解決するためには、各部門の情報をリアルタイムで統合し、一元的に管理する仕組みが不可欠です。
その仕組みを構築する上で強力なツールとなるのが、ERP(統合基幹業務システム)です。ERPを導入することで、販売実績や生産状況、在庫情報などを全社でリアルタイムに共有でき、データに基づいた精度の高い需要予測や在庫計画の立案が可能になります。余剰在庫の削減は、企業の持続的な成長を実現するための重要な経営課題です。まずは自社の課題を整理し、その解決策としてERPがどのような価値をもたらすのか、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。