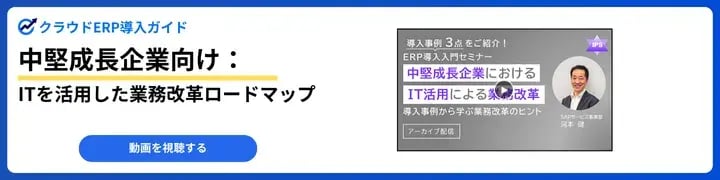新しいシステムの導入プロジェクトにおいて、「どのような機能を実現するか」という「機能要件」に議論が集中しがちです。しかし、どれほど優れた機能を持っていても、「動作が遅い」「頻繁に停止する」「セキュリティが脆弱」といった問題を抱えていては、そのシステムの価値は大きく損なわれてしまいます。
こうしたシステムの"使いやすさ"や"信頼性"といった品質を根底から支えるのが、今回解説する「非機能要件」です。この非機能要件の定義が、プロジェクトの成否、ひいてはビジネスの成果を大きく左右すると言っても過言ではありません。
この記事で分かること
- 非機能要件の正確な定義と、機能要件との明確な違い
- 非機能要件がビジネスの成功に不可欠である理由
- 定義すべき非機能要件の具体的な項目一覧とそのポイント
- SaaS時代における非機能要件の新たな考え方
- プロジェクトを成功に導く非機能要件の定義・評価の実践的アプローチ
非機能要件とは?システム品質を支える「縁の下の力持ち」
システム開発プロジェクトを成功させるためには、機能要件と非機能要件の両方をバランス良く定義することが不可欠です。まず、この二つの要件の根本的な違いと、非機能要件が持つ本質的な役割を理解しましょう。
非機能要件の定義
非機能要件とは、システムが提供する具体的な「機能(何ができるか)」以外の、品質や特性に関する要件全般を指します。言い換えれば、「どのように動作するか」を定義するものです。
これには、システムの応答速度(性能)、安定稼働率(可用性)、情報の安全性(セキュリティ)、将来の拡張のしやすさ(拡張性)、運用・メンテナンスのしやすさ(運用・保守性)などが含まれます。ユーザーがシステムを快適かつ安心して使い続けるための、いわば土台となる品質要件です。
定義した非機能要件をRFPに落とし込む具体的なステップは、『失敗しないRFPの書き方を5ステップで解説!経営層が知るべき最新トレンドとは』 を参照すると整理しやすくなります。
機能要件との明確な違い
機能要件と非機能要件の違いを、オンラインの経費精算システムを例に考えてみましょう。
- 機能要件(何ができるか):
- 交通費や出張費などの経費を申請できる。
- 上長が申請を承認または否認できる。
- 経理担当者が承認されたデータを会計システムに連携できる。
- 非機能要件(どのようにできるか):
- 性能: 申請ボタンをクリックしてから、3秒以内に完了画面が表示される。
- 可用性: 業務時間内(平日9時〜18時)は99.9%以上の時間、システムが利用可能である。
- セキュリティ: 従業員の個人情報や経費データは暗号化して保存される。
このように、機能要件が「実装すべきこと」のリストであるのに対し、非機能要件は「達成すべき品質レベル」の基準を示すものと言えます。
なぜ非機能要件が経営課題の解決に直結するのか
非機能要件は単なる技術的な仕様ではなく、経営層や企画部門こそが理解し、主導すべき重要な経営課題です。なぜなら、非機能要件の品質レベルが、ビジネスの成果に直接的な影響を与えるからです。
ユーザーの生産性と満足度に与える影響
例えば、システムの応答速度が数秒遅いだけで、従業員の作業効率は大きく低下します。これが全社規模で起これば、その生産性の損失は莫大なものになります。また、頻繁にシステムが停止すれば、業務そのものが滞り、機会損失につながります。優れた非機能要件は、従業員がストレスなく業務に集中できる環境を提供し、組織全体の生産性を向上させるのです。
事業継続性と信頼性の担保
セキュリティ要件の不備は、情報漏洩などの重大なインシデントを引き起こし、企業の社会的信用を失墜させかねません。また、障害からの復旧時間が長引けば、それだけ事業停止期間も長くなり、直接的な売上損失や顧客離れにつながります。堅牢な非機能要件は、事業継続計画(BCP)の根幹をなし、企業の信頼性を担保する上で不可欠です。
将来のビジネス変化への対応力
ビジネス環境が目まぐるしく変化する現代において、システムが将来の拡張や変更に柔軟に対応できるか(拡張性・保守性)は極めて重要です。拡張性の低いシステムは、事業の成長に合わせて機能を追加しようとした際に、多大な改修コストや時間が必要となります。将来を見据えた非機能要件を定義しておくことが、変化に強い持続可能な経営基盤を築くことにつながるのです。
【一覧】非機能要件の主要6項目と定義のポイント
非機能要件は多岐にわたりますが、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「非機能要求グレード」などを参考に、一般的に以下の6つの主要なカテゴリに分類して整理されます。ここでは各項目の概要と、経営視点で押さえるべきポイントを解説します。
1. 可用性(Availability)
システムを継続的に利用できる度合いを示す要件です。「システムが止まらないこと」に関わります。
- 定義のポイント:
- 稼働率: 年間を通じてシステムが稼働すべき時間の割合を定義します(例:99.9%)。
- 復旧時間: 障害発生時に、どれくらいの時間でシステムを復旧させるかを定めます(目標復旧時間:RTO)。
- バックアップ: データのバックアップ頻度や、どの時点のデータまで復旧させるか(目標復旧時点:RPO)を定義します。
可用性やセキュリティをどのように評価項目に落とし込むかは、『RFPの評価基準とは?失敗しないベンダー選定を実現する作り方と評価項目を徹底解説【テンプレート付】』 を参考に検討するとスムーズです。
2. 性能・拡張性(Performance / Scalability)
システムの処理能力や応答速度、将来の負荷増加への対応能力に関する要件です。「システムの速さや成長への追随」に関わります。
- 定義のポイント:
- レスポンスタイム: ユーザーが操作してからシステムが応答するまでの時間(例:全画面の95%は3秒以内に表示)。
- スループット: 単位時間あたりに処理できる件数(例:1時間あたり1,000件の受注を処理可能)。
- 拡張性: 将来のユーザー数やデータ量の増加に、どのように対応できるかを定義します(例:サーバー増設によるスケールアウトが可能か)。
3. 運用・保守性(Serviceability / Maintainability)
システムリリース後の日常的な運用や、障害発生時のメンテナンスのしやすさに関する要件です。「システムの維持管理のしやすさ」に関わります。
- 定義のポイント:
- 監視: システムの稼働状況やエラーを24時間365日監視できるか。
- 障害通知: 障害発生時に、管理者へ自動で通知される仕組みがあるか。
- メンテナンス: 定期的なメンテナンスによるサービス停止時間や、その事前通知方法を定めます。
4. 移行性(Portability)
既存のシステムやデータから、新しいシステムへ円滑に移行するための要件です。「システム切り替えのスムーズさ」に関わります。
- 定義のポイント:
- データ移行: 既存システムのどのデータを、どのような形式で、いつまでに移行するか。
- 移行期間中の並行稼働: 新旧システムを一時的に並行稼働させる必要があるか。
5. セキュリティ(Security)
不正アクセスや情報漏洩といった脅威から、システムやデータを守るための要件です。「システムの安全性」に関わります。
- 定義のポイント:
- アクセス制御: 誰が、どの情報にアクセスできるかを制御する仕組み(認証・認可)。
- データの暗号化: 通信経路やデータベースに保存される重要データを暗号化するか。
- 脆弱性対策: 不正アクセスを防ぐための対策(WAFの導入など)や、定期的な脆弱性診断の実施。
6. システム環境・エコロジー
システムの動作環境や、環境への配慮に関する要件です。
- 定義のポイント:
- 対応ブラウザ・OS: ユーザーが利用するPCやスマートフォンのOS、Webブラウザのバージョンを指定します。
- 省エネルギー: クラウドサービスの利用によるサーバー消費電力の削減など、環境への配慮を定義します。
システムの種類で変わる非機能要件の扱い方
非機能要件の重要性は普遍的ですが、その扱い方は導入するシステムの種類によって大きく異なります。特に、従来型の受託開発と現代の主流であるSaaSとでは、アプローチが根本的に変わります。
従来型(オンプレミス・受託開発)の場合:「定義」が中心
従来型のシステム開発では、インフラの構築からアプリケーションの開発まで、すべてを自社の要件に合わせて作り込みます。そのため、非機能要件は「自社で達成すべき品質目標をゼロから定義するもの」という位置づけになります。サーバーの冗長構成やバックアップの仕組み、セキュリティ対策などを細かく設計し、それを実現するための開発をベンダーに依頼します。
SaaS・クラウド型の場合:「評価・選定」が中心
一方、SaaSを利用する場合、性能や可用性、セキュリティといったシステムの基盤は、基本的にSaaSベンダーが提供するサービスレベルに依存します。ユーザーがインフラやアプリケーションの内部構造を直接コントロールすることはできません。
したがって、SaaS導入における非機能要件は、「自ら細かく定義するもの」から、「ベンダーが提示するサービスレベル(SLA)や仕様を、自社の要求レベルと照らし合わせて評価・選定するもの」へと、その役割がシフトします。
SaaS導入の成功法則「Fit to Standard」とは
このSaaSの特性を最大限に活かす考え方が「Fit to Standard(フィットトゥスタンダード)」です。これは、システムの標準機能に合わせて自社の業務プロセスを見直し、カスタマイズを最小限に抑える導入アプローチです。
Fit to Standardを前提とすると、機能要件の定義は比較的シンプルになります。その一方で、システムの品質を担保する非機能要件の重要性は、むしろ高まります。なぜなら、自社でコントロールできない領域が増える分、ベンダーが提供する非機能要件のレベル(SLA、セキュリティ認証、サポート体制など)が、自社のビジネス要件を本当に満たせるのかを、より一層シビアに見極める必要があるからです。
非機能要件を定義・評価する際の実践的アプローチ
では、具体的にどのように非機能要件の定義や評価を進めればよいのでしょうか。プロジェクトを成功に導くための実践的なアプローチを紹介します。
1. 経営層・業務部門を巻き込み、要求レベルを決定する
非機能要件は、技術者だけの問題ではありません。「どの程度のシステム停止なら事業として許容できるか」「個人情報を扱う上で、どのレベルのセキュリティを担保すべきか」といった問いは、経営判断そのものです。プロジェクトの初期段階で、情報システム部門だけでなく、経営層や実際にシステムを利用する業務部門を巻き込み、ビジネスインパクトの観点から要求レベルの合意形成を図ることが不可欠です。
2. ベンダーに任せきりにせず、主体的に要件を提示する
非機能要件は専門性が高いため、ついベンダー任せにしたくなりがちですが、これは非常に危険です。ベンダーはあくまで一般的なレベルでの提案しかできません。自社のビジネスにとって何が重要なのかを主体的に考え、RFP(提案依頼書)を通じて明確に要件を提示することで、初めて自社に最適な提案を引き出すことができます。
3. 「非機能要求グレード」などのフレームワークを活用する
ゼロから非機能要件を洗い出すのは大変な作業です。前述したIPAの「非機能要求グレード」のような、網羅的に項目が整理されたフレームワークを活用することで、検討漏れを防ぎ、効率的に要件定義を進めることができます。
4. 定量的な指標で定義し、客観的に評価する
「高速であること」「安全であること」といった曖昧な表現ではなく、「応答時間3秒以内」「ISMS認証を取得していること」のように、できるだけ客観的に測定・評価できる定量的な指標で定義することが重要です。これにより、RFPに対するベンダーからの提案を公平に比較でき、導入後の受け入れテストの基準も明確になります。
【FAQ】非機能要件に関するよくある質問
ここでは、非機能要件に関して経営層やプロジェクト担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
非機能要件はIT部門に任せきりで良いのでしょうか?
いいえ、任せきりは危険です。非機能要件のレベルは、事業の継続性やコスト、顧客満足度に直結する経営判断です。「システムが1時間停止した場合の事業損失はいくらか」といったビジネスインパクトを最も理解しているのは、経営層や業務部門です。IT部門と連携し、ビジネスの視点から必要な品質レベルを決定することが不可欠です。
非機能要件のレベルを上げると、コストも高くなるのでは?
はい、一般的に非機能要件のレベルを上げるとコストは増加する傾向にあります。例えば、システムの稼働率を99.9%から99.99%に上げるためには、インフラの冗長化などでコストが大幅に増えることがあります。だからこそ、自社のビジネスにとって「どのレベルが最適か」を見極めることが重要です。過剰品質は不要なコスト増に、品質不足は将来のビジネスリスクにつながります。
SaaSの場合、非機能要件はベンダーのSLAを鵜呑みにするしかないのですか?
鵜呑みにすべきではありません。SLA(サービス品質保証)は、ベンダーが保証する最低限のサービスレベルです。まずは、そのSLAが自社のビジネス要求を満たしているかを評価する必要があります。また、SLAでカバーされない領域(例:アプリケーション固有のパフォーマンス、データバックアップの範囲など)についても、詳細な仕様を確認し、必要に応じて追加の対策や契約を検討することが重要です。
「可用性99.9%」と言われても、具体的にどう判断すれば良いですか?
パーセンテージを具体的な時間に換算して、ビジネスインパクトを評価することが有効です。「99.9%」は、年間で約8.76時間のサービス停止を許容することを意味します。一方、「99.99%」であれば約52分です。この停止時間が自社の業務にどのような影響を与えるかを具体的にシミュレーションすることで、必要な可用性レベルを判断しやすくなります。
Fit to Standardでシステムを導入する場合、非機能要件で特に注意すべき点は何ですか?
特に「セキュリティとガバナンス」「API連携の柔軟性」「ベンダーのサポート体制」の3点が重要になります。クラウド上にデータを保管するため、自社のセキュリティポリシーを満たしているか、データ管理の権限設定が柔軟に行えるかは厳密に評価する必要があります。また、他のSaaSとの連携が前提となるため、APIの仕様や拡張性も重要な選定基準です。最後に、自社でコントロールできない部分が増えるからこそ、障害発生時などに迅速かつ的確なサポートを受けられるかが、安定運用の鍵を握ります。
まとめ
本記事では、システム開発の成否を分ける「非機能要件」について、その本質的な役割から具体的な項目、そしてSaaS時代における新たな考え方までを解説しました。
機能要件がシステムの「骨格」だとすれば、非機能要件はシステムの「心臓や神経」に相当します。いくら立派な骨格を持っていても、心臓や神経が正常に機能しなければ、その価値を発揮することはできません。
特に、SaaSの導入が主流となり、Fit to Standardのアプローチが推奨される現代において、非機能要件を正しく理解し、評価・選定する能力は、もはやIT担当者だけでなく、すべての経営層・リーダーにとって不可欠なスキルと言えるでしょう。
この記事が、貴社にとって最適なシステムを導入し、その真の価値を引き出すための一助となれば幸いです。まずは自社の業務にとって「本当に重要な品質は何か」を問い直すことから、情報収集を始めてみてはいかがでしょうか。