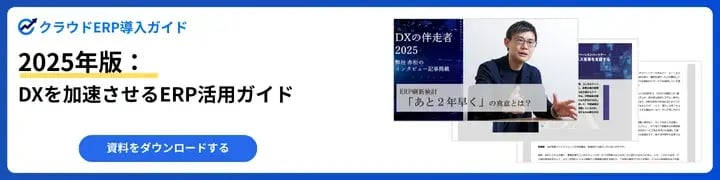製造業のデジタル化が進む中、「ERP」や「MES」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、それぞれの違いや導入メリットがよくわからないと感じていませんか?
本記事では、ERPとMESの基本概念から、両者を連携させるメリットまで詳しく解説し、製造業における業務改善のヒントをお届けします。
関連記事はこちら
ERPとMESそれぞれの基本概念

製造業のデジタル化が進む中で、「ERP」と「MES」という言葉を耳にする機会が増えています。これらはどちらも業務の効率化に欠かせないシステムですが、目的や役割、導入対象が大きく異なります。
それぞれの基本的な概念について詳しく見ていきましょう。
ERPとは?企業全体を管理する統合システム
ERP(Enterprise Resource Planning)とは、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を一元管理し、全社的な業務プロセスを最適化するための統合システムです。
会計や販売、在庫、人事、生産など、部門ごとに管理されていたデータを1つのプラットフォームに統合することで、情報のサイロ化を防ぎ、迅速な意思決定が可能となります。特に、クラウド型ERPの普及により、中堅・中小企業でも導入しやすくなりました。
MESとは?工場現場を管理する製造実行システム
MES(Manufacturing Execution System)は、製造現場での作業実行をリアルタイムで管理・監視するためのシステムです。
生産指示から、作業進捗の記録、不良品の管理、設備稼働率の把握まで、工場内のあらゆる情報を収集・分析し、現場の「可視化」を実現します。
MESの目的は、製造オペレーションの効率化と品質の安定化であり、現場の即応性が重要視されます。ERPが経営層向けの「全体最適化ツール」であるのに対し、MESは現場向けの「実行支援ツール」といえるでしょう。
ERPとMESの導入対象とできること
ERPとMESは、それぞれ異なる対象と目的で導入されます。
- ERPの対象:経営層~各部門
- MESの対象:製造現場の作業者、管理者
ERPは会計・販売・在庫・人事・購買など、全社レベルのデータを統合管理し、経営判断の基盤を支える役割を担います。一方でMESは、現場の実行データをリアルタイムで収集・管理し、現場のオペレーション改善に直結する情報を提供します。
導入を検討する際は、それぞれの目的と使用される現場のニーズを明確にすることが重要です。経営全体の可視化や業務効率の向上を目指すならERPが、現場作業の効率化や製造プロセスの精度向上が求められるならMESが適しています。
業務課題や経営課題に応じて、適切なシステムを選定することが重要です。
「ERPだけ」「MESだけ」では不十分なのか

ERPとMESは、それぞれ異なる得意分野を持つため、片方だけでは全社的な最適化が難しい場面もあります。
ERPは企業全体の基幹業務を管理する統合システムとして強力な武器になりますが、製造現場のリアルタイムな状況把握には不向きです。一方でMESは製造現場に特化して即時性のある判断をサポートしますが、経営層の視点から企業全体を俯瞰する役割までは担えません。
ここでは、それぞれの限界と役割分担を理解し、「なぜ両方活用すべきか?」を掘り下げていきます。
ERP:製造現場のリアルタイム把握は苦手
ERPは経営層にとって必要な情報を網羅的に統合できますが、製造現場で発生するリアルタイムの出来事には即応できない場合があります。例えば、設備の稼働状況や作業進捗、不良品の発生など、細かく変化する情報を正確かつ迅速に把握するのは苦手です。
これは、ERPがもともと「全体最適化」の視点で設計されているためであり、リアルタイム性よりも統合性や制度性を重視した構造であることが背景にあります。
そのため、現場の迅速な判断や柔軟な対応が求められる場面では、ERPだけでは限界があります。
MES:全社経営管理まではカバーできない
MESは製造現場における生産指示や進捗管理、品質管理などをリアルタイムでサポートするシステムであり、現場に即した業務改善には非常に有効です。しかし、会計情報や販売データ、人事データといった経営全体に関わるデータの統合・分析まではカバーしていません。
つまり、MESは「部分最適化」には優れていますが、「全体最適化」には限界があるのです。経営層が企業全体の状況を把握して意思決定を行うには、MESだけでは情報が不足してしまうため、ERPの存在が必要不可欠です。
機能の専門性の違いを理解することが鍵となる
ERPとMESは異なる目的と専門性を持つシステムであり、その違いを理解することが導入成功の鍵です。
ERPは会計・在庫・販売・人事など企業全体の基幹業務を統合し、経営判断をサポートします。MESは製造現場の工程管理や作業者単位での進捗・品質管理など、現場の即応性に特化しています。
両者は「どちらが優れているか」でなく、「自社のどの業務に適しているか」で選定すべきです。導入の成否は機能の優劣ではなく、業務課題との適合度で決まります。
ERPとMESそれぞれの得意領域

ERPとMESは、それぞれ異なる業務領域に特化したシステムです。
ここでは、ERPとMESがどの業務に強みを持ち、どのように役割分担されるのかを具体的に整理していきます。
ERPが得意な領域(会計・販売・在庫管理など)
ERPは企業の基幹業務を横断的に管理・統合できるのが大きな特徴です。
具体的には以下のような領域に強みを発揮します。
- 会計管理:仕訳、決算、原価計算、予算管理などの財務データを一元管理し、経営判断を支える正確な情報を提供する
- 販売管理:受注・見積・請求・入金の各業務を連携させ、顧客対応の迅速化や販売プロセスの可視化を実現する
- 在庫管理:リアルタイムでの入出庫状況や棚卸データを把握し、適正在庫の維持や欠品防止を可能にする
- 人事・給与管理:従業員情報、勤怠、給与、育成履歴などを一元管理し、労務リスクの低減と効率化につながる
- 購買管理:発注から納品、検収、支払までを統合し、調達コストの最適化を図る
ERPは「全社の基盤業務」を横断的かつ戦略的に管理するための中心的な役割を担います。
MESが得意な領域(製造指示・現場データ収集・進捗管理)
MESは製造現場に特化した管理システムであり、リアルタイムな情報収集と即応性を重視する業務に強みを持っています。
以下のような領域で効果を発揮します。
- 製造指示の管理:ERPなど上位システムから受け取った生産計画をもとに、製造現場での具体的な作業指示を作成・配信する
- 現場データの収集・記録:作業進捗、不良品発生、設備稼働率、作業者の作業内容など、多様なデータをリアルタイムで収集する
- 進捗・品質の管理:作業ステータスや製造ロットの追跡、品質チェック結果などを管理し、生産のスムーズな流れと品質の安定をサポートする
MESはこれらの機能を通じて、「現場の正確な状況把握」と「迅速な対応」を実現するシステムです。
製造業でよくあるERPとMESの役割分担
製造業におけるERPとMESは、それぞれの得意領域を活かしつつ、明確な役割分担のもとで運用されるケースが一般的です。
以下はその代表的な分担例です。
- ERPが担う領域:生産計画の作成、原価計算、在庫管理、販売管理、購買管理、人事・労務管理など
これらは主に「計画」や「経営」の視点からの業務であり、生産に必要な資材を手配するための在庫確認や、販売予測に基づく生産指示などが該当する - MESが担う領域:現場への製造指示、作業者の割り当て、設備稼働状況の監視、作業進捗・品質データの収集など
これらは「実行」や「現場対応」に直結する業務であり、ERPからの生産指示を受けて、それを現場でどう実施するかを細かく管理する
ERPとMESを連携させるメリット

ERPとMESはそれぞれ独立したシステムとしても機能しますが、連携させることで情報の流れがシームレスになり、業務全体の最適化を実現できます。
ここでは、連携によって得られる主なメリットを解説します。
リアルタイムなデータ統合で迅速な判断が可能
ERPとMESを連携させる最大のメリットの1つが、リアルタイムでのデータ統合による迅速な判断の実現です。MESが製造現場から収集する作業進捗や設備稼働、品質状況などのデータを、ERPへ即時に反映させることで、経営層は現場の最新状況をタイムリーに把握できます。
例えば、生産中の異常や遅延が即座にERPに通知されることで、資材手配や納期調整などの早期判断が可能になります。これにより、計画と実行のギャップを最小化し、業務全体のスピードアップと正確性向上につながるでしょう。
また、在庫や原価、販売予測といった経営指標も、現場の実態に基づいてリアルタイムで精度を高められるため、経営判断の質そのものが大きく向上します。
生産現場と経営層の情報ギャップ解消
ERPとMESを連携させることで、生産現場と経営層の間に存在する情報ギャップを効果的に解消できます。
MESが収集する現場の詳細なデータがERPに自動連携されることで、経営層もリアルタイムで現場の状況を把握することが可能です。
これにより、現場で起きている問題が経営層に伝わらず対応が遅れるといった、従来の課題が解消されます。例えば、生産ラインで発生したトラブルや工程の進捗遅延、不良品の傾向といった情報を即座にERP上で確認できることで、根本的な対策の立案やリスク回避がスムーズに行えるようになります。
また、現場も経営層の意図を理解しやすくなり、現実的かつ納得感のある経営判断が現場レベルで実行に移されるようになります。
部門間の連携が円滑になる
ERPとMESを連携させることで、製造・調達・品質・営業など、部門をまたぐ情報のやり取りがスムーズになります。これまで部門ごとに情報管理が分断されていた場合、情報の重複や認識のズレが生じやすく、無駄な手戻りや対応の遅れが発生していました。
しかし、両システムをつなぐことで、例えば製造現場のトラブルや進捗の遅れといった情報が、リアルタイムで他部門にも共有されます。その結果、販売部門は納期への影響を即座に把握し、顧客対応の前倒しが可能になります。
こうした連携の効果は、単なる業務効率の改善にとどまりません。社内全体での情報共有が活性化し、組織の一体感や対応力の向上にもつながります。
現代のERPはMES領域をどこまでカバーできるのか

近年のERPは進化を遂げ、従来はMESが担っていた製造現場の機能まで一部対応できるようになってきました。
ここでは、最新ERPがどこまでMESの役割を補えるのか、また連携によって得られる可能性と連携パターンについて詳しく解説します。
最新ERPには生産現場を支援する機能も搭載
近年のERPは、生産スケジュールの自動化、在庫のリアルタイム管理、IoT機器との連携による設備や作業状況の可視化といった、現場業務を支援する機能が充実しています。
これらの機能により、製造現場で発生する情報もERP内に集約され、調達・在庫・販売といった他部門とのデータ連携がスムーズになります。
従来は「経営層向け」の印象が強かったERPですが、現在では現場のオペレーションも支える統合プラットフォームとして、企業全体の生産性向上に貢献する存在へと進化しています。
ERP×MES統合で得られる可能性
ERPとMESを統合的に活用することで、経営層と製造現場がリアルタイムでシームレスにデータを共有できる環境が整います。
MESの現場データをERPに取り込むことで、在庫削減や生産性向上、納期遵守率の改善といった成果につながります。
ERPを「情報の中枢」、MESを「現場の実行支援」として補完関係を明確に位置づけることで、単なる連携にとどまらず、全社的な最適化を実現する統合活用が可能です。
ERPとMESの連携パターン①:役割分担型
役割分担型は、ERPとMESを「疎結合」で連携させるシンプルかつ実践的なモデルです。ERPは製造指示、購買・販売、在庫計画などの計画・管理領域を担当し、MESは現場での製造実行や進捗管理、品質記録といった実行領域を担います。
この構成により、ERPは「上流の計画」、MESは「現場の実行」という明確な役割分担が可能になります。製造現場で収集された実績データは、MESからERPへフィードバックされ、経営判断や原価計算、納期調整などに活用されます。
現場と経営が相互補完的に連携しながら、情報の一元管理と業務効率化を実現できるのが、このモデルの大きな特徴です。
ERPとMESの連携パターン②:垂直統合型
垂直統合型は、ERPがMESの機能を内包し、計画から実行までを単一のプラットフォームで管理する「密結合」モデルです。
例えば、最新のERP製品(SAP S/4HANAなど)では、製造オーダー管理、作業指示、進捗・品質の記録といったMES相当の機能があらかじめ搭載されており、別途MESを導入せずとも一体的な製造管理が可能となっています。
この構成では、計画・指示・実行・実績の全工程が同じシステム上で完結するため、システム間連携に伴うデータの不整合や遅延を最小化できます。
まとめ
ERPとMESは、それぞれ異なる役割と得意分野を持つシステムです。
ERPは企業全体の基幹業務を統合・最適化し、MESは製造現場の実行をリアルタイムに支援します。それぞれ単体での活用も可能ですが、両者を連携・統合することで、経営と現場の情報がシームレスにつながり、全社的な業務最適化が実現できます。
自社の業務課題に応じて、適切な導入と連携のあり方を見極めることが、デジタル化成功への第一歩となるでしょう。