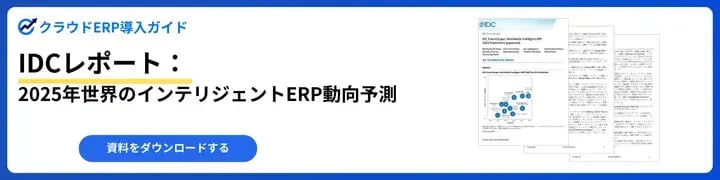「SAPは使いにくい」と耳にすることがありますが、それは本当でしょうか。確かに一部ではそういわれてきた経緯がありますが、近年の進化によって、SAPはより使いやすく、導入しやすいシステムへと進化しています。
本記事では、SAPが使いにくいとされる理由と、その誤解を解きほぐす最新の動向を解説します。
SAPは本当に使いにくい?

「SAPは使いにくい」と感じる方が多いのは事実です。
SAPは、企業のあらゆる業務を網羅できる多機能かつ柔軟性の高いERPシステムである反面、操作に慣れるまでに時間がかかることもあります。
特に導入初期は覚えることが多く、戸惑いを覚える場面が少なくありません。
しかし、近年はユーザーインターフェース(UI)の改良や支援ツールの充実により、使いやすさが着実に向上しています。
SAPはなぜ使いにくいと感じられるのか?

SAPが使いにくいとされる背景には、操作の複雑さや導入プロセスでの課題が関係しています。ここでは、操作性の問題だけでなく、導入時の目的共有不足や知識・ナレッジの欠如といった要因を詳しく解説します。
操作が複雑で直感的ではないという評価が根強い
旧来のSAP GUIは取引コードを覚える必要があり、業務知識を前提とした構造のため、初心者にとって直感的とはいえないものでした。
画面内の情報量が多く、レイアウトも固定的で操作性に乏しいという指摘もありました。また、ユーザーごとの業務や役割に応じた最適化が不十分だったことも、使いにくさを助長した要因です。
ユーザー体験(UX)への配慮が後回しにされていたことが「SAP=使いにくい」という評価の背景にあります。
導入目的の共有不足
SAP導入を経営層が決定しても、その目的が現場まで正しく共有されていないケースが多く見受けられます。経営層が導入に深く関与せず、現場任せにすると「なぜこのシステムを使うのか」という根本的な意義が理解されず、ただ業務が複雑になったと感じられがちです。
目的の不透明さは導入の納得感を欠き、結果的に「SAPは使いにくい」という印象を強めてしまいます。
導入する側のSAPに関する知識不足・ナレッジ不足
SAP導入において、導入側のSAPに関する知識不足は大きな課題となります。
特に、SAPが持つ標準機能の内容や目的を十分に理解せずに進めると、本来不要なカスタマイズや非効率な設計が発生しやすくなります。
また、導入プロジェクトに関わるメンバー間で知識のレベルに差があると、要件定義や設計段階でのコミュニケーションミスが起こりやすく、最終的に「思っていたより使いにくいシステム」になってしまうリスクが高まります。
過剰なカスタマイズが使いにくさを招く
SAP導入時に自社の業務に過度に合わせたカスタマイズを行うと、操作が複雑になり、運用負荷も増加します。
その結果、標準UIとの乖離や属人化が進み、「使いにくい」と感じられることがあります。こうした事態を防ぐために、近年では「Fit to Standard」の考え方が普及しつつあり、標準機能に合わせて業務を見直すアプローチが推奨されています。
SAPが使いにくいと言われる背景とは?

SAPは豊富な標準機能を備えた高機能なERPですが、「使いにくい」と感じられる背景には、ユーザビリティが後回しにされてきた歴史があります。ここでは、標準機能では解消されない理由や運用面での課題について解説します。
標準機能があるのに“使いにくい”と感じられる理由
SAPの標準機能は非常に豊富で業務処理を幅広くカバーしていますが、それでも「使いにくい」と感じられる背景には、その設計思想が大きく関係しています。
ユーザビリティよりも業務統制や制度対応に重きを置いた設計のため、自由度が低く、操作に制限が多いのが特徴です。
さらに、機能重視・業務特化型の構造は専門知識を持たないユーザーにとって理解が難しく、結果的に使いづらさを感じさせてしまう要因となっています。
オンプレミス型ERP時代の運用課題
オンプレミス型ERPが主流だった時代、システムは自社で構築・運用されていたため、柔軟な変更が難しく、アップデートや保守にも多大なコストと時間がかかっていました。
さらに、UIの刷新も限定的で、業務に合わせたカスタマイズが使いにくさを助長する要因となっていました。
しかし現在の主流はクラウド型ERPとなり、迅速なアップデートやUIの進化により、かつての「使いにくい」という評価は見直されつつあります。
使いにくかったSAPのUIは進化している

かつて「使いにくい」と言われたSAPのUIは、クラウド移行とS/4HANA化の進展により大きく変化しています。
ユーザー層の拡大に伴い、従来の専門職に加えて経理・購買・人事部門や一般社員、外部業者、管理職など、より幅広いユーザーがSAPを扱うようになりました。
これに対応するため、2010年代後半以降、SAPはUX向上を戦略の中心に据え、SAP Fioriの登場により「誰でも使えるERP」へのシフトが加速しました。
スマートフォンやタブレット対応も進み、操作性が格段に向上しています。
現代のSAPが実現する利便性

かつて「使いにくい」とされたSAPですが、SAP FioriやAI、標準化手法の導入により、誰でも直感的に使えるERPとして進化を遂げています。ここでは、その具体的な利便性について詳しく解説します。
SAP Fioriによる直感的なUX
SAP Fioriは、従来のSAP GUIとは異なり、UXを重視して設計された次世代のUIです。
モバイル対応や役割ベースの画面構成により、各ユーザーが必要とする情報にすばやくアクセスできる仕組みが整っています。視覚面でも、直感的で不要な項目を非表示にできるため、画面の見やすさと操作性が大きく向上しました。
また、フィルタやソートといったExcelに近い操作が標準で備えられており、日常業務に馴染みやすい環境が整っています。
これにより、ITの専門知識がなくても業務をスムーズに進められるようになりました。
AIアシスタント「Joule」の活用
SAPのAIアシスタントJoule(ジュール)は、SAPに組み込まれた生成AIベースのAIエージェントです。
ユーザーが業務で扱うデータを理解し、文脈に応じた提案や自動処理を行うことで、作業効率を大幅に高めることが可能です。例えば、必要なレポートの自動生成やダッシュボードのカスタマイズ、問い合わせへの即時回答などが実現します。
Jouleは、複雑な操作を必要とせず、日常業務の中で直感的に使えるよう設計されており、SAPの利便性をさらに高める革新的なツールです。
Fit to Standard導入による標準化推進
従来のSAP導入では、自社業務に合わせたカスタマイズが多く、運用の複雑化や属人化を招く原因となっていました。
こうした課題を解決するアプローチとして注目されているのがFit to Standardです。
これはSAPが提供する標準機能を最大限活用し、業務プロセスをシステムに合わせて見直すという考え方です。これにより、導入コストや期間を抑えながら、安定した運用と将来的なアップデート対応が可能になります。
標準化は、長期的な視点でSAP活用の効率性を高める重要な鍵となります。
関連記事:SAPプロジェクトの進め方のコツとは?SAP ActiveやFit to Standardについて解説
FioriとGUIの進化によるUI/UX改善
SAPのUI/UXは、従来のSAP GUIからSAP Fioriへの移行によって大きく改善されています。
従来のGUIは情報が密集し、取引コードの記憶や操作に習熟を要するものでしたが、SAP Fioriでは視覚的にわかりやすいデザインと、役割に応じた画面構成により直感的な操作が可能になりました。

出典:SAP Learning Journey: "Introducing the User Interface"
また、既存のGUI画面を簡易的にカスタマイズできる「Screen Personas」のようなノーコードツールも登場し、ユーザー自身が使いやすい画面を自由に構築できる柔軟性も加わりました。
これにより、ユーザー中心の操作体験が現実のものとなっています。
関連記事:SAP Fioriとは?SAPのユーザー体験を向上させる新しいUI/UXを解説
中堅・中小企業におけるSAP導入成功事例
SAPは大企業向けという印象が強いかもしれませんが、近年では中堅・中小企業においても導入が進み、業績改善や業務効率化に成功した事例が増えています。ここでは、その代表的な事例をご紹介します。
赤城乳業:短期間導入で売上拡大・不動在庫の削減に成功
冷菓メーカーとして全国的に知られている赤城乳業は、複雑化していた原価管理や在庫管理、部門間の情報連携の課題を解消するため、SAP ERPを導入しました。
食品業界向けに最適化されたSAPの「食品テンプレート」を活用することで、必要最低限のカスタマイズで済み、プロジェクトの複雑化を防ぎながら導入を完了しました。
この取り組みにより、従来課題となっていた在庫の偏りや不動在庫を大幅に削減しました。不動在庫は従来の1/4〜1/5程度まで圧縮され、在庫コストの大幅削減に成功しています。
さらに、PSI(生産・販売・在庫)の情報をリアルタイムで可視化できるようになったことで、現場の判断力が高まり、従業員の改善提案活動の活発化にもつながりました。
マツモトプレシジョン:DX推進で利益改善
精密機械部品メーカーのマツモトプレシジョンは、2021年にSAP ERPを導入し、DX推進の第一歩を踏み出しました。
導入にあたっては、アドオン開発を行わずに、既存業務の流れをSAPの標準機能に合わせるという「Fit to Standard」の方針を採用しています。これにより初期費用の抑制を実現し、会社全体の業務を見直す絶好の機会と捉えて改革に着手しました。
SAP導入後は、製品ごとの原価や利益の可視化が可能となり、収益性の低い製品の見直しによって営業利益率を3%改善。売上総利益も30%増加するなど、数値面でも大きな成果が現れました。
さらに、全社員の給与を4%引き上げるなど、経営成果を従業員に還元する取り組みも実施しています。
「SAP=使いにくい」は過去の話

かつて「使いにくい」といわれたSAPも、近年では大きく進化しています。ユーザーの声を反映した設計と支援体制の強化で、誰でも使いこなせるシステムへと変貌を遂げています。
ユーザー中心設計で大幅に進化したSAP
SAPは近年、「ユーザー中心設計」を重視した製品開発に注力しています。その象徴が、モダンなデザインと直感的な操作性を兼ね備えたSAP Fioriです。
SAP Fioriでは、役割に応じて必要な機能のみを表示し、不要な項目は非表示にすることで、ユーザーが迷わず操作できるナビゲーションを実現しています。
さらに、視覚的なアイコンやスマート検索機能により、操作ミスや迷いが減り、業務効率も大幅に向上しました。
従来のように専門知識を前提とせず、すべての社員が直感的に操作できるUIに刷新されたことで、「誰でも使えるERP」への進化が現実のものとなりました。
導入時や運用面でのユーザーサポートが充実
SAPでは導入初期から運用フェーズまで、ユーザー支援の仕組みが格段に進化しています。とくに注目されているのが「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」の活用です。
これは、ユーザーが操作に迷わないように、リアルタイムで画面上にナビゲーションや入力手順を表示する仕組みで、初めての操作でも迷うことなく利用できます。
また、ガイド付き操作や役割別チュートリアル、検索機能付きの操作ヘルプなども整備されており、トレーニングを受けなくても自走できる環境が整っています。
これにより、システム定着率の向上や教育コストの削減といった導入効果も期待できるでしょう。
標準化とベストプラクティスの活用
SAPでは、販売管理・購買管理・生産管理・会計・人事など、あらゆる業務領域に対応したベストプラクティスと呼ばれる標準業務プロセスがあらかじめ整備されています。
これにより、現場ごとに複雑なカスタマイズを加える必要がなくなり、システム導入時の混乱や属人化を防止できます。
各業務カテゴリにおける成功事例や運用ノウハウがテンプレート化されているため、ユーザーは迷わず操作でき、業務定着もスムーズです。
こうした標準化により、導入スピードの向上、運用コストの削減、さらには将来的なアップデートの容易さといった多くの利点が得られます。
Fit to Standardという考え方のもと、業務そのものを標準機能に合わせて見直すアプローチが主流となりつつあります。
まとめ
「SAPは使いにくい」といわれていたのは過去の話です。
確かにかつては操作が複雑で、導入目的や運用ルールの共有不足などから、定着しにくい面がありました。しかし現在では、SAP Fioriによる直感的なUIの進化、AIアシスタントの搭載、Fit to Standardの浸透により、導入・運用のしやすさが飛躍的に向上しています。
中堅・中小企業でも成功事例が相次ぎ、「誰でも使えるERP」としての信頼性を確立しています。SAPは単なる業務システムではなく、企業の成長を支える強力な経営基盤となり得る存在です。
これからの時代、正しい理解と適切な導入によって、SAPはより多くの企業にとって価値あるツールとなるでしょう。