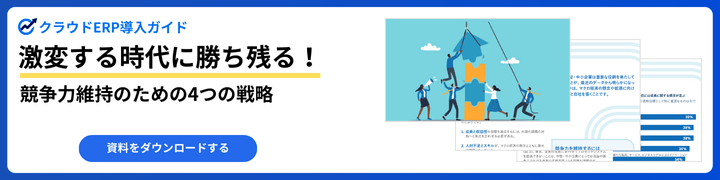この記事で分かること
- 経営計画発表会の基本的な定義と企業経営における役割
- 3ヶ月前からの具体的な準備ステップとスケジュール管理
- すぐに使えるアジェンダテンプレートと進行の流れ
- 対面・オンライン・ハイブリッド形式のメリット・デメリット比較
- 計画を実行に移すためのアフターフォロー手法

経営計画発表会を、社員の士気を高め、全社一丸となって目標達成へ向かうための重要な機会にできていますか?
本記事では、開催目的の明確化から、すぐに使えるアジェンダのテンプレート、具体的な準備手順、オンライン開催の注意点まで、計画を絵に描いた餅で終わらせないための運営ノウハウを徹底解説しています。
経営計画発表会とは?数字や方針を伝えるだけで終わらせないために
企業の持続的な成長において、経営層と従業員が一つの方向を向いて進むことは不可欠です。しかし、「策定した経営計画が現場まで浸透しない」「部門間の連携が取れず、全社最適の視点が欠けている」といった課題に直面している経営者の方も少なくないでしょう。こうした課題を解決し、組織全体を活性化させるための重要なイベントが「経営計画発表会」です。
経営計画発表会は、単に数字や方針を伝えるだけの形式的な場ではありません。経営層のビジョンや想いを全従業員と共有し、会社全体のベクトルを合わせることで、計画達成に向けた一体感を醸成する極めて重要な機会です。
この章では、経営計画発表会の基本的な定義と、企業経営において果たすべき役割について掘り下げて解説します。
経営計画発表会の定義と基本的な役割
経営計画発表会とは、事業年度の始まりなど特定の節目に、経営陣が策定した中長期の経営計画や当該年度の事業計画を、全従業員に向けて公式に発表・共有する場を指します。この発表会を通じて、従業員一人ひとりが自社の現状と目指すべき未来を正しく理解し、自身の業務が経営目標達成にどう貢献するのかを認識することが可能になります。
経営計画発表会が担う基本的な役割は、多岐にわたります。主な役割を以下の表にまとめました。
| 役割 | 具体的な内容と期待される効果 |
|---|---|
| 方針の共有と浸透 | 企業のビジョンやミッション、今期の重点戦略といった会社の進むべき方向性を全社で共有します。経営トップ自らの言葉で、計画策定の背景にある想いや市場環境認識を伝えることで、従業員の深い理解と共感を促し、計画の浸透度を高めます。 |
| 目標達成への意識統一 | 全社、各部門、そして個人が目指すべき目標を明確に示し、連携させます。これにより、組織全体のベクトルが揃い、従業員は日々の業務における自身の役割と責任を再認識できます。全員が同じ目標に向かうことで、組織としての一体感が生まれます。 |
| 従業員の士気向上 | 会社の未来像や成長戦略を共有することは、従業員にとって自社の将来性への期待感を抱かせることに繋がります。また、前期の成果を称える表彰などをプログラムに組み込むことで、従業員のモチベーションを高め、新たな気持ちで新年度をスタートさせる「区切り」としての役割も果たします。 |
| 社内外へのコミットメント表明 | 社内に向けては、経営陣が「本気で計画を達成する」という強い決意と覚悟を示す場となります。また、取引先や金融機関などの外部関係者を招待する場合、自社の健全性や将来性をアピールし、強固な信頼関係を築く機会にもなります。 |
失敗しない!経営計画発表会の準備スケジュール【3か月前からの実践ステップ】
経営計画発表会を成功させるためには、周到な準備が不可欠です。場当たり的な準備では、伝えたいメッセージがぶれてしまい、参加者の士気を高めるどころか、かえって不信感を招きかねません。ここでは、発表会の3ヶ月前から当日までの準備を、具体的なステップに分けて解説します。
【3か月前】目的とターゲットを明確化し、発表会の骨格を固める
経営計画発表会の成否は、この初期段階の設計で9割決まると言っても過言ではありません。まずは時間をかけて、発表会の骨格を固めていきましょう。
誰に何を伝えたいのかを定義する
最初に定義すべきは、発表会の「目的」です。なぜ、時間とコストをかけてまで経営計画発表会を実施するのでしょうか。この目的が曖昧なままでは、以降のすべての準備が的外れなものになってしまいます。
例えば、目的として以下のようなものが考えられます。
- 全社一丸となって目標達成に向かうための、ビジョンと戦略の共有
- 社員一人ひとりの役割と目標への理解を深め、当事者意識を醸成する
- 部門間の連携を強化し、サイロ化を防ぐためのコミュニケーション機会の創出
- 前期の成果を称え、社員のモチベーションを高める
目的を明確にしたら、次に「誰に(ターゲット)」、「何を(メインメッセージ)」伝えたいのかを具体的に定義します。参加するのは経営層だけでしょうか。それとも、管理職、一般社員、さらには内定者まで含めるのでしょうか。参加者の役職や立場によって、響く言葉や求める情報は異なります。ターゲットを具体的に想定することで、メッセージの解像度が一気に高まります。
開催形式と予算を決定する
目的とターゲットが定まったら、それを実現するための最適な「開催形式」と、必要な「予算」を決定します。開催形式は大きく分けて「対面」「オンライン」「ハイブリッド」の3つがあり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。(各形式の詳細は後の章で解説します)
例えば、一体感の醸成や熱量の伝達を最優先するなら対面形式、遠隔地の社員も参加しやすくコストを抑えたいならオンライン形式が候補となるでしょう。目的に合わせて最適な形式を選択することが重要です。
形式が決まったら、概算予算を策定します。必要な項目を漏れなく洗い出し、費用対効果を検討しましょう。
| 大項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 会場費 | 会場レンタル料、控室利用料、付帯設備使用料(プロジェクター、音響設備など) |
| コンテンツ制作費 | 発表資料デザイン、動画制作、印刷費 |
| 運営費 | 司会者や外部講師への謝礼、運営スタッフ人件費、配信機材レンタル・オペレーター費用(オンライン・ハイブリッドの場合) |
| その他 | 表彰記念品、参加記念品、懇親会費用、交通費・宿泊費 |
【1か月前】アジェンダと資料を整え、伝わる構成を設計する
開催まで1ヶ月となったら、設計した全体像を具体的な形に落とし込んでいきます。参加者の集中力を維持し、メッセージを効果的に伝えるためのクリエイティブな工夫が求められるフェーズです。
参加者を惹きつけるプログラム構成
経営層が一方的に話し続けるだけの発表会では、参加者は受け身になり、内容が頭に入ってきません。社員を「お客様」ではなく「当事者」として巻き込むためのプログラムを意識的に組み込むことが成功の鍵です。
- 双方向性の確保: 質疑応答の時間を十分に確保するだけでなく、パネルディスカッション形式で複数の役員や部門長が登壇し、多角的な視点を示すのも有効です。
- 参加型コンテンツ: 事業部ごとの目標発表や、グループワークを取り入れ、参加者自身が考え、発言する機会を設けます。
- 感動と称賛の演出: 優秀な成績を収めた社員やチームを表彰する「表彰式」は、モチベーション向上に絶大な効果を発揮します。受賞者の功績を具体的に紹介し、全社で称賛する雰囲気を作りましょう。
全体の時間配分も重要です。人間の集中力には限界があります。長時間のセッションが続く場合は、適度に休憩を挟むなど、参加者が常に新鮮な気持ちで臨めるような配慮が必要です。
分かりやすい発表資料の作成ポイント
発表資料は、メッセージを視覚的に補強し、理解を助けるための重要なツールです。以下のポイントを意識して、分かりやすい資料作成を心がけましょう。
- One slide, One message: 1枚のスライドに情報を詰め込みすぎず、最も伝えたいメッセージを1つに絞ります。
- ビジュアル化の徹底: 文字ばかりの資料は敬遠されます。グラフ、図、イラスト、写真などを積極的に活用し、直感的な理解を促しましょう。特に、企業の成長戦略や業績推移などは、グラフを用いることで説得力が格段に増します。
- 専門用語を避ける: 経営層にとっては当たり前の用語でも、一般社員には馴染みがない場合があります。誰が聞いても理解できる、平易な言葉で表現することを徹底してください。
- デザインの統一感: 会社ロゴの配置ルールや基本カラー、フォントなどを定め、すべての発表資料でトーン&マナーを統一します。これにより、発表会全体に統一感が生まれ、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。
【1週間前】運営マニュアルとリハーサルで“当日トラブル0”を目指す
いよいよ開催まで1週間。この段階では、当日の運営をスムーズに進めるための最終確認と、不測の事態に備えるためのリハーサルが中心となります。
運営マニュアルの作成と役割分担
当日の運営を円滑に進めるため、詳細な「運営マニュアル」を作成し、スタッフ全員で共有します。マニュアルには、以下の項目を盛り込みましょう。
- 当日のタイムスケジュール(準備、本番、撤収まで)
- 会場レイアウト、機材配置図
- 運営スタッフの役割分担表と動き方の指示
- 緊急時の連絡体制と対応フロー
- 配布資料や備品の一覧
特に役割分担は重要です。司会進行、受付・誘導、会場設営、音響・照明・PC操作、オンライン配信担当、写真・動画撮影など、各担当者を明確に定め、それぞれの責任範囲と連携方法を確認しておきます。
| 役割 | 担当者 | 主な任務 |
|---|---|---|
| 全体統括 | 〇〇 | 全体の進捗管理、最終意思決定、トラブル対応の指揮 |
| 司会進行 | △△ | 開会・閉会の挨拶、プログラムの進行、登壇者の紹介 |
| 機材・配信担当 | □□ | PC操作、音響・照明の調整、オンライン配信の監視、機材トラブル対応 |
| 受付・誘導 | ◇◇ | 参加者の受付、座席への誘導、資料配布 |
当日のトラブルを想定したリハーサルの実施
リハーサルは、単なる発表練習の場ではありません。本番と全く同じ環境・時間軸で一連の流れを通し、潜在的な課題を洗い出して対策を講じるための最終チェックの機会です。
特に、以下の点は入念に確認しましょう。
- 時間管理: 各プログラムが時間通りに進行するか。発表者の持ち時間は適切か。
- 機材連携: パソコンとプロジェクターの接続、マイクの音量、照明のタイミング、オンライン配信の映像・音声は問題ないか。
- 登壇者の動き: 登壇・降壇のスムーズな動線は確保されているか。
- トラブルシューティング: 「映像が映らない」「音声が出ない」「発表者が時間オーバーした」といった、起こりうるトラブルをあえて発生させ、対応手順を確認するシミュレーションも有効です。
念入りなリハーサルが、当日のスムーズな運営と、予期せぬトラブルへの冷静な対応を可能にします。
すぐに使える!経営計画発表会のアジェンダ例と進行の流れ
経営計画発表会を成功させるためには、練り上げられたアジェンダが不可欠です。ここでは、多くの企業で採用されている標準的なアジェンダ構成を、タイムスケジュールの目安とともにご紹介します。自社の目的や文化に合わせてカスタマイズする際の土台としてご活用ください。
| 時間(目安) | 内容 | 主な発表者 |
|---|---|---|
| 5分 | 開会の挨拶 | 司会者 / 役員 |
| 20分 | 前期業績の振り返り | 担当役員 / 経理責任者 |
| 60分 | 中期経営計画と今期の重点戦略 | 代表取締役社長 |
| 30分 | 事業部ごとの方針と行動計画 | 各事業部長 |
| 30分 | 優秀社員・チームの表彰 | 代表取締役社長 / 役員 |
| 15分 | 質疑応答 | 経営陣 |
| 5分 | 閉会の挨拶 | 代表取締役社長 / 役員 |
開会の挨拶
まず、司会者あるいは担当役員から開会が宣言されます。
ここでは、経営計画発表会の目的と意義を改めて共有し、参加者の意識を統一します。また、参加者への感謝を伝え、これから始まる発表会への期待感を醸成する重要な役割を担います。来賓を招いている場合は、このタイミングで紹介することもあります。
前期業績の振り返り
次に、前期の経営計画に対して、どのような結果であったかを具体的に報告します。単に売上や利益といった財務数値を報告するだけでなく、計画(Plan)と実績(Do)の差異を明確にし、その成功要因や課題(Check)を分析することが重要です。この振り返りを通じて得られた教訓が、今期の計画の説得力を高めます。良かった点は称賛し、課題は真摯に受け止める姿勢を示すことで、組織全体の学びへと繋げます。
中期経営計画と今期の重点戦略
このセクションが経営計画発表会の最も重要な核となります。企業の未来像を示し、全社員のベクトルを合わせるための時間です。
全社方針と目標数値の共有
まず代表取締役社長から、企業のビジョンやミッションに基づいた3~5年後の中期的な展望が語られます。市場環境や競合の動向分析を踏まえ、「なぜ今、我々はこの方向を目指すのか」というストーリーを情熱を持って伝えることが求められます。その上で、今期のスローガンや、売上高・利益率といった具体的な目標数値を全社で共有します。この目標は、挑戦的でありながらも達成可能で、かつ測定可能なものであることが理想です。
事業部ごとの方針と行動計画
全社方針という大きな羅針盤が示された後、各事業部がどのようにその方針を実現していくのか、具体的な航海図を発表します。ここでは各事業部長が登壇し、全社目標を達成するために自部門が担う役割(KGI/KPI)と、具体的なアクションプランを明確に説明します。これにより、社員一人ひとりが日々の業務と会社の大きな目標との繋がりを理解し、「自分ごと」として計画を捉えることができるようになります。
優秀社員・チームの表彰
計画の発表だけでなく、前期の頑張りを称える場を設けることも、社員のモチベーション向上に極めて有効です。会社の成長に大きく貢献した社員やチームを具体的な功績とともに表彰することで、他の社員の模範となり、組織全体にポジティブな競争意識と一体感が生まれます。表彰基準を明確にし、全社員が納得できる形で実施することが成功の鍵です。
質疑応答
経営陣と社員が直接対話する貴重な機会です。社員からの質問に真摯に答えることで、経営計画への理解を深め、疑問や不安を解消します。双方向のコミュニケーションは、経営の透明性を高め、社員の当事者意識を醸成する上で欠かせません。事前に質問を受け付けたり、リアルタイムで質問を投稿できるツールを活用したりと、活発な質疑応答を促す工夫も有効です。
閉会の挨拶
最後に、代表取締役社長や役員が、発表会全体を総括します。発表された計画の重要性を改めて強調し、全社員が一丸となって目標達成に向かうことへの期待と激励のメッセージを力強く伝えます。参加者全員の士気を高め、明日からの行動へと繋げるための重要な締めくくりです。
経営計画発表会を“成功イベント”に変える3つの鍵
経営計画発表会は、単に計画を伝達するだけの場ではありません。社員一人ひとりの意識を変え、組織全体の実行力を最大化するための重要なキックオフイベントです。ここでは、発表会を形骸化させず、真に成功へと導くために不可欠な3つの鍵について、具体的なアプローチとともに解説します。
①経営層の熱意と覚悟を伝えるスピーチ設計
社員の心を動かし、計画達成へのモチベーションを点火する最大のエネルギー源は、経営層、特に社長自身の「熱意」と「本気度」に他なりません。ロジカルな戦略や数字だけでは、人は動きません。経営層がどのような想いでこの計画を策定し、未来をどう描いているのかを、自らの言葉で情熱的に語ることが極めて重要です。
社長自身の言葉でビジョンを語る
コンサルタントが作成したような美辞麗句を並べた資料を読み上げるだけでは、社員の心には響きません。企業のトップとして、これまでの道のりを振り返り、時には失敗談も交えながら、なぜ今この変革が必要なのか、そしてその先にある会社の未来がいかに素晴らしいものであるかを、臨場感あふれる自身の言葉で語りかけることが求められます。その熱量が社員に伝播し、計画への共感と信頼を醸成する第一歩となります。
揺るぎない覚悟を示す
経営計画は、決して平坦な道のりではありません。時には困難な課題や予期せぬ障害が待ち受けているでしょう。そうした困難に直面した際に、先頭に立って乗り越えていくという経営層の揺るぎない覚悟を示すことが不可欠です。質疑応答の場で社員からの厳しい質問や意見にも真摯に耳を傾け、誠実に対話する姿勢を見せることで、社員は「このリーダーについていけば大丈夫だ」という安心感と信頼感を抱くことができます。
②社員を「お客様」ではなく「当事者」にする仕掛け
社員が経営計画を「他人事」として捉え、受け身の姿勢で参加していては、発表会の効果は半減してしまいます。社員一人ひとりが「会社の未来を創る主役は自分自身である」という「当事者意識」を持つための仕掛けをプログラムに組み込むことが成功の鍵となります。
双方向性を意識したプログラム設計
一方的なプレゼンテーションに終始するのではなく、社員が能動的に参加できる時間を設けることが重要です。例えば、以下のような双方向性のあるプログラムが考えられます。
- グループワーク・ワークショップ:全社方針を受けて、各部門やチームで「自分たちは具体的に何に取り組むべきか」を議論し、発表する時間を設けます。これにより、計画が自分たちの業務に直結していることを実感できます。
- リアルタイムアンケートやQ&Aツール:オンラインツールを活用し、参加者が匿名で質問や意見を投稿できるようにします。これにより、普段は発言しにくい社員からも本音を引き出し、活発な議論を促すことができます。
計画と個人の接続を促す
全社的な大きな目標だけでは、社員は日々の業務との繋がりを見出しにくいものです。全社方針から事業部、部門、そして個人の目標へと、計画がどのようにブレイクダウンされるのかを具体的に示すことが求められます。発表会の中で、各部門の責任者が自身の言葉で部門方針と具体的なアクションプランを語るセッションを設けることも有効です。これにより、社員は自身の役割と責任を明確に認識し、日々の業務に意味を見出すことができます。
③発表会後のアフターフォローで「計画を動かす仕組み」を作る
経営計画発表会で高まった熱気や一体感を、一過性のイベントで終わらせず、持続的な行動へと繋げるためのアフターフォローの仕組みこそが、計画の成否を分けます。発表会はゴールではなく、あくまでスタート地点であるという認識を全社で共有することが重要です。
進捗を可視化し、共有する仕組み
策定した計画が絵に描いた餅とならないよう、定期的に進捗を確認し、全社で共有する仕組みを構築する必要があります。具体的な施策としては、以下のようなものが挙げられます。
| 施策 | 目的 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 月次・四半期レビュー会議 | 定期的な進捗確認と軌道修正 | 各部門のKPI進捗を報告し、課題や成功事例を共有。経営層がフィードバックを行う。 |
| 社内報やビジネスチャットでの発信 | 継続的な情報共有と意識の維持 | 計画に関連する取り組みや成果を定期的に発信し、社員の関心を維持する。 |
| 1on1ミーティング | 個人レベルでの目標接続と支援 | 上司と部下が定期的に面談し、経営計画と連動した個人目標の進捗確認や課題解決のサポートを行う。 |
| 評価制度との連動 | 計画達成へのコミットメント向上 | 経営計画の達成への貢献度を人事評価の項目に組み込み、社員のインセンティブを高める。 |
特に、部門ごとに管理されているExcelや古いシステムでは、全社横断でのリアルタイムな進捗把握が困難になりがちです。計画の進捗状況を誰もがリアルタイムで正確に把握し、データに基づいた迅速な意思決定を下せるようにするためには、経営基盤となるシステムの刷新も視野に入れることが、計画実行の確度を飛躍的に高める上で不可欠と言えるでしょう。
対面・オンライン・ハイブリッド?経営計画発表会の開催形式を比較
経営計画発表会を成功させるためには、その目的に合わせて最適な開催形式を選択することが不可欠です。近年、働き方の多様化に伴い、発表会の形式も多様化しています。従来の対面形式に加え、オンライン形式、さらには両者を組み合わせたハイブリッド形式が選択肢として挙げられます。それぞれの形式が持つ特性を深く理解し、自社の状況や目的に最も合致する方法を選ぶことが、計画の浸透度と社員のエンゲージメントを最大化する鍵となります。
対面形式のメリットとデメリット
対面形式は、役員と社員が一つの場所に集う最も伝統的な開催方法です。物理的な空間を共有することで生まれる一体感や熱量の伝わりやすさは、他の形式にはない大きな魅力と言えるでしょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 非言語コミュニケーションによる一体感の醸成が容易で、経営層の熱意や本気度が伝わりやすい。 | 会場費、参加者の交通費や宿泊費など、物理的なコスト負担が大きい。 |
| 参加者が同じ空間にいるため集中力が持続しやすく、メッセージへの没入感が高い。 | 遠隔地の拠点に勤務する社員や、育児・介護などの事情を抱える社員の参加が困難な場合がある。 |
| 休憩時間や懇親会などを通じて、部署を超えた偶発的なコミュニケーションが生まれやすい。 | 会場の収容人数に限りがあり、全社員が参加できない可能性がある。 |
オンライン形式のメリットとデメリット
オンライン形式は、インターネットを活用してどこからでも参加できる柔軟性が最大の特徴です。特に、複数の拠点を持つ企業やリモートワークを主体とする企業にとっては、有効な選択肢となります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 遠隔地の拠点や在宅勤務の社員も参加可能で、全社的な情報共有を公平に行える。 | 一体感の醸成や熱意の伝達が難しい傾向にあり、参加意識に個人差が出やすい。 |
| 会場費や移動コストが不要なため、開催コストを大幅に削減できる。 | 参加者側の通信環境に依存するため、映像や音声のトラブルが発生するリスクがある。 |
| 発表会の様子を録画し、後日アーカイブとして共有することで、当日参加できなかった社員も内容を確認できる。 | 一方的な情報伝達になりがちで、参加者の集中力が途切れやすい。 |
ハイブリッド形式のメリットとデメリット
ハイブリッド形式は、主要な会場での対面開催とオンライン配信を組み合わせた、比較的新しい開催方法です。対面とオンライン、双方の利点を享受できる可能性がある一方で、運営の複雑さという課題も抱えています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 対面とオンラインの長所を両立できる可能性があり、参加者が自身の状況に合わせて参加形式を選べる。 | 最も運営が複雑で、機材や人員のコストがかかる。 |
| より多くの社員に参加機会を提供しつつ、中心となる会場では一体感を醸成できる。 | 対面参加者とオンライン参加者の間で、得られる情報や体験に格差が生まれやすい。 |
| オンライン配信の仕組みを活用することで、イベント後のアーカイブ共有もスムーズに行える。 | 音響や映像の配信クオリティを両立させるための高度な技術とノウハウが求められる。 |
経営計画の実行と迅速な意思決定を支えるDX基盤「SAP S/4HANA Cloud」
経営計画発表会で示されたビジョンや戦略も、日々のオペレーションに落とし込まれ、その進捗が的確に把握できなければ「絵に描いた餅」で終わってしまいます。多くの企業で、部門ごとに導入されたシステムや無数のExcelファイルによってデータがサイロ化し、全社横断でのリアルタイムな状況把握を困難にしています。このような課題は、変化の激しい現代市場において、迅速な経営判断の遅れや機会損失に直結する深刻な問題です。
こうした課題を解決し、経営計画の着実な実行とデータに基づいた迅速な意思決定を可能にするのが、SAP S/4HANA Cloudのような次世代のクラウドERP(Enterprise Resource Planning)です。
SAP S/4HANA Cloudが実現するデータドリブン経営
SAP S/4HANA Cloudは、企業の「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」といった経営資源を一元的に管理し、活用するための考え方であるERPをクラウド上で実現するシステムです。最新のテクノロジーを活用することで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を強力に推進し、データドリブン経営へと変革します。
リアルタイムな経営状況の可視化
SAP S/4HANA Cloudを導入することで、売上や利益、在庫、キャッシュフローといった重要な経営指標が、経営コックピット(ダッシュボード)上でリアルタイムに可視化されます。従来、報告のためだけに多大な時間を費やしていたデータ集計作業から解放され、経営層はいつでもどこでも最新のビジネス状況を正確に把握し、次の一手を打つための時間に集中できます。これにより、勘や経験だけに頼らない、客観的なデータに基づいた経営判断が可能になります。
精度の高いシミュレーションと将来予測
市場の変動や新たな事業機会に対し、どのような影響が出るのかを事前にシミュレーションできる機能も強みです。例えば、原材料価格の変動が製品原価や利益率に与える影響や、新規投資がキャッシュフローに与えるインパクトなどを即座に分析できます。これにより、変化を先読みし、より確度の高い戦略的意思決定をプロアクティブに行うことが可能になります。
部門間の連携強化と業務プロセスの標準化
営業、製造、購買、会計、人事といった全部門のデータが一つのプラットフォームで統合管理されるため、部門間の壁がなくなり、情報連携がスムーズになります。SAPが長年にわたりグローバルで蓄積してきた様々な業種のベストプラクティス(標準業務プロセス)が組み込まれているため、自社の業務プロセスを標準化し、全社最適の視点で業務効率を抜本的に改善することが可能です。
中堅企業がクラウドERPを導入するメリット
特に成長を目指す中堅企業にとって、クラウドERPの導入は大きなメリットをもたらします。従来のオンプレミス型ERPと比較して、その利点は明確です。
| 比較項目 | SAP S/4HANA Cloud (クラウドERP) | 従来のオンプレミス型ERP |
|---|---|---|
| 初期投資 | 低く抑えられる(サーバー等のインフラが不要) | 高額になりがち(サーバー購入費、ライセンス費など) |
| 導入期間 | 比較的短い | 長期にわたる傾向 |
| 運用・保守 | ベンダー側で実施するため、運用負荷とコストを大幅に削減できる | 自社で専門人材を確保し、対応する必要がある |
| 拡張性・柔軟性 | ビジネスの成長に合わせて柔軟に拡張可能 | 拡張には追加の投資や開発が必要 |
| 最新技術の活用 | AIや機械学習など、最新のテクノロジーが自動でアップデートされる | バージョンアップには多大なコストと時間がかかる |
経営計画の実現に向けた次の一歩
経営計画発表会で掲げた高い目標を達成するためには、それを支える強固な経営基盤が不可欠です。SAP S/4HANA CloudのようなクラウドERPは、単なるITツールではなく、経営戦略と日々の業務執行をデジタルで繋ぎ、企業の変革と成長を加速させるエンジンとなり得ます。まずは自社の経営課題を整理し、その解決策としてDX基盤の刷新を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ|経営計画発表会は「スタート地点」。
全社員で未来を創ろう
本記事では、経営計画発表会を成功に導くための目的設定から当日のアジェンダ例までを網羅的に解説しました。発表会の成功はゴールではなく、全社一丸となって計画を確実に実行するためのスタートです。計画の進捗をリアルタイムに可視化し、変化へ迅速に対応する意思決定を行うためには、全社の情報が集約された経営基盤が不可欠といえます。SAP S/4HANA Cloudのような次世代ERPは、その強力な基盤となります。まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。