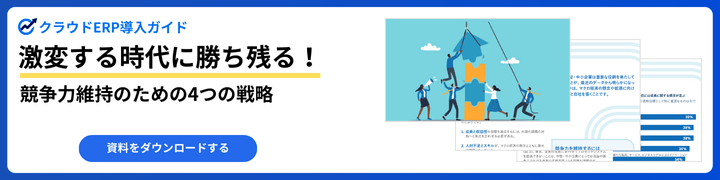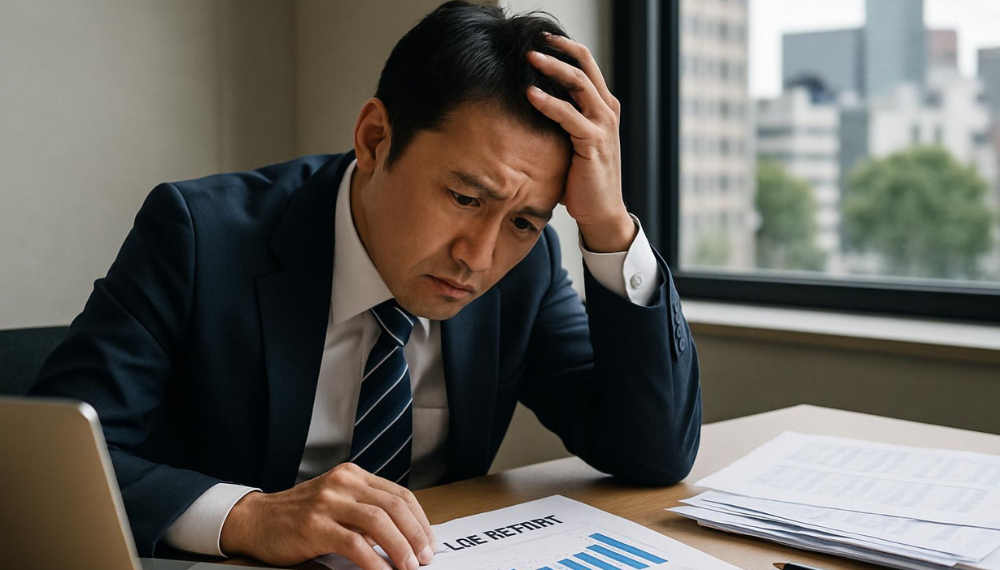
「営業目標を達成するために、月末になるといつも慌ててしまう」「なぜ目標を達成できないのか、根本的な原因がわからない」多くの営業組織がこのような課題を抱えています。
その原因は、結果だけを追いかける従来の「予実管理」にあるかもしれません。安定的に目標を達成し続ける強い営業組織には、未来の売上につながる"材料"を管理する「予材管理」という考え方が不可欠です。
本記事では、予材管理の第一人者が提唱するメソッドを基に、その本質から具体的な実践方法、成果を最大化するポイントまでを網羅的に解説します。単なる精神論ではなく、科学的なアプローチで営業目標を達成するための仕組みづくりを、この記事で手に入れてください。
この記事で分かること
- 予材管理の基本的な意味と、営業組織にもたらす効果
- 「結果」を追う予実管理と「未来」を創る予材管理の決定的な違い
- 予材管理を導入する具体的なメリットと注意すべきデメリット
- 明日から始められる予材管理の実践5ステップ
- 予材管理を成功に導くためのポイントとおすすめツール・テンプレート
この記事を最後まで読めば、なぜ今まで目標達成が困難だったのかが明確になり、継続的に成果を出し続けるための具体的なアクションプランを描けるようになります。
予材管理とは?営業組織に欠かせない"売上の源泉管理"
予材管理とは、将来の売上につながる可能性のある営業案件や見込み材料である「予材」を管理し、計画的に目標達成を目指す営業マネジメント手法です。
多くの企業で、月の売上目標が未達に終わった際、その原因が十分に分析されないまま翌月を迎えてしまうケースは少なくありません。予材管理は、こうした状況を打開し、営業目標の達成を個人のスキルや市況といった不確定要素に委ねるのではなく、組織的かつ科学的なアプローチで実現するために注目されています。
この手法の根幹には、「最低でも目標は達成する」という考え方があります。 従来の営業手法が、設定された目標に対してぎりぎりの案件数や商談数で活動するのに対し、予材管理ではあらかじめ目標の2倍の予材を準備しておくという特徴的な考え方を採用します。
これにより、予期せぬ失注や顧客都合のキャンセルといった不測の事態が発生しても、他の予材でカバーすることが可能となり、目標達成の確度を飛躍的に高めることができるのです。 つまり、予材管理は単なるノルマ管理ではなく、未来の売上を安定的に創出するための「売上の源泉」を管理する、極めて戦略的な営業プロセス管理手法と言えます。
「予材」が意味するものとは?未来の売上を作る"材料"のすべて
予材管理における「予材」とは、単に受注確度の高い商談中の案件だけを指すわけではありません。まだアプローチできていない潜在顧客から、具体的な提案段階にある見込み顧客まで、将来的に売上へ転換する可能性のあるすべての「材料」を含みます。
これらは一般的に、その確度や進捗状況に応じて以下の3つのフェーズに分類され、管理されます。
| 予材の種類 | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|
| 見込材(見込み) | ほぼ受注が確実視されている、成約確度の非常に高い案件。 | ・契約書締結待ちの案件 ・顧客から発注の内示が出ている案件 ・最終的な意思決定者が承認済みの案件 |
| 仕掛材(仕掛り) | 現在商談が進行中であったり、具体的な提案や折衝を行っていたりする案件。 | ・初回訪問を終え、提案書を作成中の案件 ・見積もりを提示し、顧客が検討中の案件 ・製品デモを実施し、フィードバック待ちの案件 |
| 白地材(白地) | まだ具体的なアプローチはできていないが、将来的に顧客となる可能性を秘めた潜在的な案件やターゲット。 | ・過去に名刺交換をしただけのリスト ・資料請求があったが未接触のリード ・自社のターゲットとなりうる未開拓の企業リスト |
予材管理では、これら3つの「材料」を常に潤沢に保有し、「白地材」から「仕掛材」へ、そして「仕掛材」から「見込材」へと計画的に育てていくプロセス全体を管理します。 これにより、営業パイプラインが枯渇することなく、継続的な売上創出が可能となるのです。
なぜ今、予材管理が注目されるのか?
市場の不確実性が増し、顧客の購買行動が複雑化する現代において、従来の勘や経験、個人の能力に依存した営業スタイルは限界を迎えています。このようなビジネス環境の変化が、予材管理の重要性を一層高めています。
多くの企業が導入している「予実管理」は、過去の実績と現在の予測を比較分析することに主眼が置かれます。しかし、目標が未達だった場合に「なぜ未達だったのか」という過去の分析に終始しがちで、未来の成果を創出するための具体的なアクションにつながりにくいという課題がありました。
一方で、予材管理は未来志向のアプローチであり、目標達成に必要な材料が今どれだけあるのか、そして今後どのように確保していくのかという「未来の数字」を可視化し、先手を打つことを可能にします。
営業活動を体系化し、プロセスを明確にすることで、営業担当者のスキルに依存しない、組織全体で安定的に高い成果を維持できる仕組みを構築できる点が、予材管理が現代の企業経営において強く求められる理由です。 成果が安定することで営業担当者の心理的な余裕が生まれ、より質の高い提案活動につながるという好循環も期待できます。
予材管理と予実管理の違い
営業成果を最大化し、企業の持続的な成長を実現するためには、適切なマネジメント手法の導入が不可欠です。その中でも、「予材管理」と「予実管理」は、多くの企業で用いられる代表的な手法ですが、その目的やアプローチは大きく異なります。両者の違いを正しく理解し、自社の状況に合わせて使い分ける、あるいは連携させることが重要です。
端的に言えば、予材管理が「未来の売上を創出するための先行管理」であるのに対し、予実管理は「過去の実績を評価し、計画との差異を分析するための事後管理」です。 それぞれの特性を詳しく見ていきましょう。
管理する「時間軸」の違い:未来志向か過去志向か
両者の最も大きな違いは、管理対象とする「時間軸」にあります。
予材管理は、「これからどうやって売上目標を達成するか」という未来に焦点を当てます。 将来の売上につながる可能性のある「予材(見込み客や商談の種)」を計画的に創出し、管理することで、目標達成の確度を高めることを目指す、未来志向のマネジメントです。 常に先の展開を見据え、能動的に市場や顧客に働きかける「攻めのマネジメント」と言えるでしょう。
一方、予実管理は、「立てた予算(計画)に対して、実績はどうだったか」という過去と現在の比較に重点を置きます。 予算と実績の差異を分析し、その原因を特定することで、経営課題の発見や次の計画サイクルの改善に繋げることを目的とします。 これは過去の活動結果を評価する、過去志向の「守りのマネジメント」と捉えることができます。
管理する「対象」の違い:プロセスか結果か
管理する対象にも明確な違いがあります。
予材管理が管理するのは、売上という「結果」に至るまでの「プロセス」です。将来の売上につながる「見込み」「仕掛り」「白地」といった予材を定義し、それぞれの量や質、そして次のステージへ移行させるための営業活動そのものを管理・改善の対象とします。 「どうすれば目標を達成できるのか」という方法論に踏み込むのが特徴です。
対照的に、予実管理が管理するのは、売上高や利益、コストといった財務数値としての「結果」です。 計画と実績という確定した数値を比較・分析することが中心であり、その結果に至った具体的なプロセスにまでは深く踏み込みません。 もちろん、差異分析からプロセスの問題が示唆されることはありますが、管理の主眼はあくまで結果の数値に置かれます。
マネジメントの「目的」の違い:目標達成の確度向上かギャップ分析か
それぞれのマネジメント手法が目指すゴールも異なります。
予材管理の最大の目的は、目標達成の「確実性」を極限まで高めることにあります。 例えば、「目標の2倍の予材を仕込む」といった戦略を用いることで、個々の案件の失注や市場の変動といった不確実性を乗り越え、安定的に目標を達成できる組織体制を構築することを目指します。
予実管理の主な目的は、計画と実績の「ギャップ」を正確に把握し、その原因を分析することです。 なぜ予算を達成できたのか(できなかったのか)を明らかにすることで、経営資源の再配分や次期計画の精度向上、潜在的なリスクの早期発見に繋げます。
比較表:一目でわかる予材管理と予実管理
これまでの違いをまとめると、以下の表のようになります。両者は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。未来を創る予材管理と、過去から学ぶ予実管理の両輪を回すことで、経営の精度は飛躍的に向上するのです。
| 比較項目 | 予材管理 | 予実管理 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 将来の売上目標達成の確度向上、リスクヘッジ | 計画と実績の差異分析、原因究明、経営課題の把握 |
| 時間軸 | 未来志向(これからどうするか) | 過去・現在志向(結果どうだったか) |
| 管理対象 | 売上に至るまでの「プロセス」(営業活動、案件の量と質) | 財務数値としての「結果」(売上、利益、コスト) |
| アプローチ | 先行管理、能動的(攻めのマネジメント) | 事後管理、受動的(守りのマネジメント) |
| 主な関与者 | 営業部門(営業担当者、営業マネージャー) | 経営層、管理部門、各事業部門 |
これらの管理手法は、Excelなどでも実践可能ですが、データの分断や入力の非効率性といった課題も生じがちです。特に全社最適の視点からは、会計システムや販売管理システムと連携し、データを一元的に可視化・分析できるERP(統合基幹業務システム)のような仕組みを導入することが、より効果的なマネジメントの実現につながります。
予材管理に欠かせない3つの要素とは?
予材管理は、将来の売上につながる可能性のある営業案件、すなわち「予材」を3つのカテゴリーに分類し、管理する手法です。 この分類によって、営業パイプライン全体を可視化し、どのステージに注力すべきかを明確にできます。
ここでは、予材管理を構成する「見込み」「仕掛かり」「白地」という3つの要素について、それぞれの役割と管理のポイントを詳しく解説します。これら3つの要素を正しく理解し、バランスを保ちながら管理することが、安定的かつ継続的な目標達成の鍵となります。
①見込み:目標達成の基盤となる「受注確実」な案件
「見込み」とは、ほぼ受注が確実視されている、確度の非常に高い案件を指します。 具体的には、顧客から発注の内示を得ている、契約締結を待つのみといった最終段階の商談がこれに該当します。
この「見込み」の金額が、目標達成における土台となります。見込み案件が目標金額に対してどれだけ積み上がっているかで、達成の確実性が大きく変わるため、マネージャーは常にこの数値を把握し、万が一失注するリスクがないかを慎重に見極める必要があります。
②仕掛かり:見込みを創出する「商談中」の案件
「仕掛かり」とは、現在進行形で商談が進んでいるものの、受注が確定していない案件のことです。 顧客への提案や見積もりの提出が完了し、検討段階に入っている状態などが含まれます。
「見込み」が不足している場合、この「仕掛かり」の中からいかに多くの案件を「見込み」へと引き上げるかが重要になります。 そのためには、顧客の課題やニーズを再確認し、最適な追加提案を行うなど、営業担当者の能動的なアクションが求められます。「仕掛かり」の量と質が、翌月以降の「見込み」を左右するため、常に一定量を維持し、それぞれの案件の進捗状況をきめ細かく管理することが不可欠です。
③白地:未来の売上を作る「潜在的」な案件
「白地」とは、まだ具体的な商談には至っていないものの、将来的に顧客となる可能性を秘めた潜在的な案件やターゲットを指します。 例えば、過去に名刺交換をしただけのリスト、資料請求があっただけのリード、これからアプローチすべきターゲット企業などが含まれます。
「白地」は、未来の「仕掛かり」や「見込み」を生み出すための源泉であり、この開拓活動を怠ると、営業パイプラインはいずれ枯渇してしまいます。 安定した売上を継続的に創出するためには、目先の「見込み」や「仕掛かり」を追いかけるだけでなく、常に「白地」に対するアプローチを続け、新たな種を蒔き続ける活動が極めて重要です。
これら3つの要素の関係性を理解し、自社の営業プロセスに当てはめて定義を明確にすることが、予材管理を成功させる第一歩となります。以下の表は、各要素の定義と具体例、そして管理におけるポイントをまとめたものです。
| 要素 | 定義 | 具体例 | 管理のポイント |
|---|---|---|---|
| 見込み | ほぼ受注が確実な案件 | ・発注の内示が出ている ・契約書締結待ち ・金額交渉が完了している |
・確実にクローズさせるための最終フォロー ・失注リスクの洗い出しと対策 |
| 仕掛かり | 商談が進行中だが、受注は未確定な案件 | ・提案・見積もり提出済み ・決裁者へのプレゼンテーション段階 ・BANT条件(予算、決裁権、必要性、導入時期)を確認中 |
・受注確度を高めるための戦略的なアプローチ ・ネクストアクションの明確化と実行 ・進捗状況の定期的なレビュー |
| 白地 | まだ商談化していない潜在的な案件・ターゲット | ・過去の名刺交換リスト ・Webサイトからの問い合わせ ・未アプローチのターゲット企業リスト |
・継続的な新規顧客開拓活動 ・マーケティング部門との連携によるリード創出 ・中長期的な関係構築(ナーチャリング) |
予材管理をするメリット5つ
予材管理は、単に営業目標を達成しやすくするだけでなく、営業組織全体に多岐にわたる好影響をもたらすマネジメント手法です。行き当たりばったりの営業活動から脱却し、科学的かつ戦略的な営業組織へと変革を促します。ここでは、予材管理を導入することで得られる5つの主要なメリットを詳しく解説します。
①目標達成の確実性を高め、売上を安定させる
予材管理の最大のメリットは、営業目標達成の確実性を飛躍的に高め、事業全体の売上を安定化させることです。 多くの企業で採用されている予実管理は、期末が近づいてから「目標に足りない」と慌てるケースが少なくありません。これは、結果(実績)を管理する手法だからです。
一方、予材管理は、目標達成に必要な「予材(将来の売上につながる可能性のある案件や材料)」をあらかじめ目標の2倍など、バッファを持って確保することを前提とします。 これにより、万が一失注する案件が出たとしても、他の予材でカバーできるため、目標達成の蓋然性が格段に高まります。常に「最低でも目標達成ができる」状態を作り出すことで、売上の波を平準化し、経営の安定に大きく貢献するのです。
②営業プロセスの課題を可視化し、改善サイクルを加速する
第2のメリットは、営業活動のプロセスにおけるボトルネックを明確に可視化できる点です。予材管理では、案件を「見込み」「仕掛り」「白地」といったステージに分類して管理します。
これにより、例えば「白地から仕掛りへの移行率が低い」「仕掛りから見込みへのリードタイムが長い」といった、どの段階に課題があるのかをデータに基づいて特定できます。課題が明確になることで、マネージャーは精神論ではなく、具体的な改善策を指示できます。
例えば、白地顧客へのアプローチ手法を見直したり、仕掛り案件に対する提案内容を強化したりといった的確なアクションが可能となり、組織全体の営業プロセス改善が加速します。
③未来志向の科学的な営業マネジメントへ転換する
予材管理は、マネジメントのあり方を大きく変革します。従来の予実管理が「過去の実績」を問い詰める"結果管理"になりがちなのに対し、予材管理は「未来の成果」を創出するための"先行管理"です。
マネージャーの役割は、部下の実績を責めることではなく、目標達成に必要な予材が足りているか、各予材の質は十分かを常にモニタリングし、未来の売上を確保するための proactive(主体的・積極的)な指導を行うことへと変化します。 これにより、勘や経験に頼った旧来のマネジメントから脱却し、データに基づいた科学的な営業組織を構築することが可能になります。
| 項目 | 予実管理(結果管理) | 予材管理(先行管理) |
|---|---|---|
| 時間軸 | 過去・現在(実績と予算の差異分析) | 現在・未来(将来の売上を創出するための活動管理) |
| 主な問い | 「なぜ目標を達成できなかったのか?」 | 「どうすれば目標を達成できるか?」 |
| マネージャーの役割 | 実績の確認と差異の追求 | 予材の量と質の確認、未来に向けた戦略指導 |
| 部下の心理 | 報告が詰められ、プレッシャーを感じやすい | 目標達成に向けた相談がしやすく、前向きに行動しやすい |
④営業担当者の主体性を引き出し、生産性を向上させる
予材管理を導入すると、営業担当者一人ひとりの生産性向上も期待できます。 目標達成までの道筋が「見込み」「仕掛り」「白地」の積み上げで可視化されるため、各担当者は今何をすべきかが明確になり、主体的に行動しやすくなります。
常に十分な予材を持つことで心理的な余裕が生まれ、目先の案件に一喜一憂することなく、より質の高い提案活動に集中できます。 結果として、個々の営業スキルが向上し、チーム全体の生産性が底上げされるのです。
⑤組織の営業力を強化し、属人化を防止する
最後に、予材管理は営業ノウハウの属人化を防ぎ、組織全体の営業力を底上げする効果があります。 ハイパフォーマーがどのようにして質の高い「予材」を創出しているのか、そのプロセスや行動が可視化・共有されるためです。
これにより、成功の型を組織の「形式知」として蓄積し、チーム全体で再現性を高めることが可能になります。 特定のエース人材に依存する不安定な組織体質から脱却し、誰もが一定水準以上の成果を出せる、強く安定した営業組織を構築することにつながるのです。
予材管理をするデメリット4つ
予材管理は、営業目標達成の確度を飛躍的に高めるポテンシャルを秘めたマネジメント手法ですが、その導入と運用には注意が必要です。メリットばかりに目を向けていると、思わぬ落とし穴にはまり、かえって組織のパフォーマンスを低下させてしまうリスクも存在します。
ここでは、予材管理を導入する際に想定しておくべきデメリットを具体的に解説します。
①管理工数の増大と現場の負担増加
予材管理を機能させるためには、これまで管理していなかった「見込み客へのアプローチ」や「長期的な関係構築中の顧客」といった、いわゆる「仕掛かり案件」までをデータとして可視化する必要があります。これにより、営業担当者の入力作業や報告業務が大幅に増加することは避けられません。
SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)といったツールを導入したとしても、その基となる情報を入力するのは現場の担当者です。
日々の活動に加え、予材の洗い出し、ステータスの更新、活動内容の記録といったタスクが増えることで、本来最も注力すべき顧客との対話や提案活動の時間が圧迫される可能性があります。結果として、現場の疲弊感を招き、エンゲージメントの低下につながるリスクがあることは十分に理解しておく必要があります。
②短期的な視点に陥り、顧客との中長期的関係構築を阻害するリスク
予材管理は「目標達成に必要な量の予材を確保する」という考え方が基本です。しかし、この「量」を追い求めるあまり、目先の数字作りに終始し、中長期的な視点での顧客育成がおろそかになる危険性があります。
例えば、「すぐに案件化しないが、将来的に大きな取引に発展する可能性のある顧客との関係構築」といった活動は、予材管理の指標上、評価されにくい傾向があります。マネジメント層が短期的な予材の量のみを追求すると、現場の営業担当者は、時間がかかるものの重要な顧客育成活動を後回しにし、手っ取り早く案件化しそうなリードばかりを追いかけるようになりかねません。これは、企業の持続的な成長の芽を摘んでしまうことにつながるため、極めて注意が必要です。
③数値目標への過度なプレッシャーによる弊害
目標から逆算して行動を管理する予材管理は、必然的に数値に対する意識を高めます。これはメリットであると同時に、過度なプレッシャーを生み出す要因にもなり得ます。目標達成へのプレッシャーが強すぎると、次のような問題が発生する可能性があります。
- 質の低い予材の乱立:目標数値を満たすため、受注確度の低い案件や、単なるリストレベルの情報を「予材」として無理に計上してしまう。
- 不正確な報告:マネージャーからの叱責を恐れ、進捗が芳しくない案件でも「順調」と報告するなど、データの信頼性が損なわれる。
- 挑戦的な活動の萎縮:失敗を恐れるあまり、新規顧客の開拓や大型案件へのチャレンジといった難易度の高い活動を避け、達成しやすい小規模な案件ばかりを狙うようになる。
これらの弊害は、予材管理の根幹である「データの正確性」を揺るがし、未来の売上予測どころか、現状把握すら困難にさせます。結果として、マネジメントの意思決定を誤らせる危険な状態に陥ります。
④導入・定着の失敗による形骸化
予材管理は、単にツールを導入したり、管理表を作成したりするだけで成功するものではありません。その目的やメリットが組織全体、特に現場の営業担当者にまで深く浸透していなければ、「マネージャーのための管理業務」と見なされ、形骸化してしまうリスクが非常に高い手法です。
目的が共有されないままトップダウンで導入を進めると、現場からは「やらされ感」が生まれ、日々のデータ入力も次第に形だけの内容になっていきます。不正確で更新されないデータが溜まった管理ツールは誰にも使われなくなり、導入にかけたコストや時間がすべて無駄になるだけでなく、組織に新たな不信感を生むことにもなりかねません。
これらのデメリットは、予材管理そのものの欠陥というよりは、導入・運用のプロセスにおける設計ミスやコミュニケーション不足に起因するものが大半です。以下の表に、主なデメリットと対策の方向性をまとめました。
| デメリット | 発生しうる問題 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 管理工数の増大 | 営業活動の圧迫、モチベーション低下 | 入力負荷の少ないSFA/CRMの選定、入力ルールの簡素化 |
| 短期的な視点への固執 | 中長期的な顧客育成の軽視、機会損失 | 長期的な関係構築活動も評価する指標の設定 |
| 過度なプレッシャー | 不正確なデータ、挑戦意欲の減退、心理的安全性の低下 | 目標未達の原因を分析し、改善策を共に考える文化の醸成 |
| 導入・定着の失敗 | 形骸化、投資コストの無駄、組織への不信感 | 導入目的の丁寧な説明、現場を巻き込んだルール作り |
予材管理を成功させるためには、これらのデメリットを事前に理解し、自社の組織文化や営業スタイルに合わせて適切にカスタマイズしながら導入を進める視点が不可欠です。
予材管理を実践する5つのステップ
予材管理は、単なる概念の理解に留まらず、日々の営業活動に落とし込み、実践してこそ真価を発揮します。ここでは、予材管理を組織的に導入し、成果へと繋げるための具体的な5つのステップを解説します。これらのステップを順に実行することで、営業組織は目標達成に向けた再現性の高い仕組みを構築できるでしょう。
① 売上目標から逆算して必要な予材量を設定する
予材管理の第一歩は、達成すべき売上目標から逆算し、どれだけの「予材」が必要かを定量的に算出することです。多くの企業では、目標の2倍の予材を準備することが一つの目安とされています。 これは、すべての案件が成約に至るわけではないという現実を踏まえ、失注や遅延といった不確実性を吸収し、目標達成の確率を最大限に高めるためのバッファを確保する考え方です。
例えば、月間の売上目標が1,000万円で、過去の実績から平均的な成約率が20%だとします。この場合、単純計算では5,000万円分の案件(商談)があれば目標を達成できることになります。しかし、予材管理ではさらにその2倍、つまり1億円分の予材を仕込むことを目指します。これにより、予期せぬトラブルが発生しても、他の予材でカバーできる体制を築きます。
| 項目 | 計算方法 | 金額 |
|---|---|---|
| 月間売上目標 | - | 1,000万円 |
| 平均成約率 | - | 20% |
| 目標達成に必要な案件総額 | 売上目標 ÷ 平均成約率 | 5,000万円 |
| 目標とする予材量(2倍ルール適用) | 必要な案件総額 × 2 | 1億円 |
この「目標の2倍」という基準は絶対的なものではなく、業種や商材、市場環境によって最適な倍率は異なります。自社の過去データや営業プロセスの特性を分析し、最適な予材量の基準を設定することが重要です。
② 予材の定義と評価基準をチームで統一する
必要な予材量が決まったら、次に「何をもって予材とするか」という定義と、その評価基準をチーム全体で統一する必要があります。この定義が曖昧だと、メンバーによって案件の捉え方が異なり、正確な予材管理ができなくなります。一般的に予材は、「見込み」「仕掛り」「白地」の3つに分類して管理されます。
- 見込み:ほぼ受注が確実視される案件。 具体的な提案が完了し、あとは契約を待つ段階。
- 仕掛り:現在商談が進行中の案件。顧客の課題をヒアリングし、提案活動を行っている段階。
- 白地:将来的に顧客となる可能性のある、まだ具体的なアプローチができていない潜在層。 新規開拓のリストや、過去に接点があったものの休眠状態にある顧客などが含まれます。
これらの定義に加え、各案件の「確度」を客観的に評価するための基準も設定します。例えば、Aランク(確度80%以上)、Bランク(確度50-80%)、Cランク(確度30-50%)のように、営業の進捗ステージと連動させた基準を設けることで、誰が見ても同じ評価ができるようになります。
| 分類 | 確度ランク | 定義 | 具体的な状態 |
|---|---|---|---|
| 見込み | A | 確度80%以上 | 最終見積提示済み、契約締結待ち |
| B | 確度50-80% | 担当者レベルでの合意形成済み、役員承認待ち | |
| 仕掛り | C | 確度30-50% | 初回提案完了、複数回商談中 |
| 白地 | D | 確度30%未満 | アポイント獲得、情報提供段階 |
こうした基準をチームで共有し、共通言語を持つことで、報告の精度が上がり、マネージャーはより的確な状況判断を下せるようになります。
③ 案件をステージ別に可視化・数値化する
定義と基準が定まったら、次はすべての案件を定義されたステージに沿って分類し、パイプラインとして可視化・数値化します。Excelやスプレッドシートでも管理は可能ですが、リアルタイム性や分析の容易さを考えるとSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)の活用が効果的です。
可視化によって、チーム全体が「どのステージに」「どれくらいの金額の案件が」「何件あるのか」を一目で把握できるようになります。これにより、例えば「仕掛り案件は多いが、見込み案件が少ない」といったパイプラインの滞留やボトルネックを早期に発見できます。
また、各ステージの案件数、金額、滞留期間などを数値化することで、営業プロセス全体の健全性を客観的に評価し、改善に向けた具体的なアクションを検討できるようになります。
④ 定期的なレビューで「質と量」を改善する
予材管理は、一度仕組みを作って終わりではありません。週次や月次など、定期的なレビューを通じて予材の「量」と「質」を常に評価し、改善し続けることが不可欠です。レビュー会議では、以下のような点を重点的に確認します。
- 予材量の充足状況:目標とする予材量(例:目標の2倍)に対して、現在の予材量は足りているか。
- パイプラインの健全性:各ステージの案件はスムーズに次のステージへ移行しているか。特定のステージで案件が滞留していないか。
- 個々の案件の進捗:進捗が遅れている案件はないか。その原因は何か。マネージャーとしてどのような支援ができるか。
- 失注分析:失注した案件の原因を分析し、今後の活動に活かせる教訓は何か。
- 白地開拓の状況:未来の予材である白地顧客へのアプローチは計画通り進んでいるか。
こうしたレビューは、単なる進捗確認の場ではなく、チーム全体の営業スキル向上やナレッジ共有の場としても機能します。 成功事例を共有し、課題に対してチームで解決策を議論することで、組織全体の営業力を底上げすることができます。
⑤ SFA・CRMツールで予材を自動的にトラッキングする
予材管理を組織に定着させ、その効果を最大化するためには、SFAやCRMといったツールの活用が極めて有効です。 これらのツールは、これまで手作業で行っていた多くのプロセスを自動化し、営業担当者の負担を軽減すると同時に、マネジメントの質を向上させます。
具体的には、以下のようなメリットが期待できます。
- 入力の効率化とデータの一元管理:顧客情報、商談履歴、進捗状況などを一元的に管理し、二重入力の手間を削減します。
- リアルタイムな可視化:営業パイプラインや予材の状況がリアルタイムでダッシュボードに反映され、常に最新の状態で状況を把握できます。
- 精度の高い売上予測:蓄積されたデータに基づき、AIなどがより客観的で精度の高い売上予測を立てる手助けをします。
- 分析とレポーティングの自動化:週次や月次のレビューに必要なレポートを自動で作成し、分析にかかる時間を大幅に短縮します。
特に、販売管理や会計システムといった基幹システム(ERP)とSFA/CRMを連携させることで、受注後の売上実績データまでシームレスに繋がり、予材から実績までの一連の流れを正確にトラッキングできるようになります。 これにより、全社的な視点でのデータドリブンな経営判断が可能となるのです。
予材管理で成果を出す3つのポイントとは?
予材管理を単なるタスク管理で終わらせず、営業組織の文化として根付かせ、継続的に成果を上げていくためには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、特に意識すべき3つのポイントを解説します。
①属人化を防ぎ、チーム全体で数字を共有する
予材管理の成否を分ける最初のポイントは、営業活動の属人化を徹底的に排除し、チーム全体でリアルタイムに数字を共有する文化を醸成することです。特定のトップセールスマンの個人的なスキルや勘に依存した営業組織は、その担当者が不在になった途端に業績が大きく傾くリスクを常に抱えています。
予材管理を導入することで、各営業担当者が保有する「予材」の量や質、進捗状況がすべて可視化されます。これにより、以下のようなメリットが生まれます。
- ノウハウの形式知化:成果を上げている担当者の行動パターン(どのような予材を、どれくらいの量、どのタイミングで仕込んでいるか)が明確になり、チーム全体の営業スキルの底上げにつながります。
- 客観的な状況把握:個人の感覚的な報告ではなく、客観的なデータに基づいてチーム全体の状況を把握できるため、より的確な戦略立案が可能になります。
- 健全な競争と協力体制の構築:メンバーそれぞれの進捗がオープンになることで、健全な競争意識が芽生えると共に、遅れているメンバーをチーム全体でサポートする協力体制も生まれやすくなります。
重要なのは、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)といったツールを活用し、情報共有を「仕組み」として定着させることです。これにより、誰もが同じ基準で数字を捉え、チーム一丸となって目標達成に向かう強固な組織基盤を構築できます。これは、部門最適に陥りがちなExcelでの個別管理では決して実現できない領域です。
②マネージャーが“未来の数字”を見て動けるようにする
従来の予実管理が「過去」の実績と「現在」の予算を比較する管理手法であるのに対し、予材管理は「未来」の売上、つまり将来の成果につながる可能性のある材料を管理する手法です。したがって、マネージャーの役割は、過去の結果を問いただす「評価者」から、未来の成果を創出するための「戦略家」へとシフトします。
マネージャーは、チーム全体の予材の量と質のバランスを常に監視し、目標達成のために「今、何をすべきか」を判断しなくてはなりません。例えば、以下のような状況判断と具体的な指示が求められます。
- 「目標達成に必要な予材の量が2倍に足りていない。来週はチーム全体で新規リード獲得のための活動に集中しよう」
- 「A君は予材の量は十分だが、受注確度の高い案件の割合が低い。今週は既存顧客への深耕営業に時間を割いて、案件の質を高めるようアドバイスしよう」
- 「特定の製品に関する案件がパイプラインの途中で停滞する傾向がある。製品知識の勉強会や、成功事例の共有会を実施してテコ入れを図ろう」
このように、マネージャーが未来の数字(予材)から逆算して先手を打てるようになることが、予材管理を成功させるための鍵となります。問題が発生してから対処する後手の管理ではなく、問題の発生を未然に防ぎ、常に目標達成への最短ルートを走るためのプロアクティブなマネジメントが実現します。
③成功企業の共通点は「量×質」の両輪マネジメント
予材管理で継続的に成果を上げている企業に共通しているのは、「量」と「質」という2つの軸を両輪で追いかけるマネジメントを徹底している点です。営業活動において、量が不足すれば目標達成はおろか、質の高い案件を選ぶことすらできません。一方で、質を無視して量ばかりを追いかけても、受注につながらない無駄な活動が増え、営業担当者は疲弊してしまいます。
「量」と「質」を効果的に管理するためには、それぞれの指標を明確に定義し、計測し続けることが不可欠です。これらの指標を常に観測し、バランスの取れた営業活動を推進することが、持続的な成長の原動力となります。
| 管理の軸 | 主な管理指標(KPI)の例 | マネジメントのポイント |
|---|---|---|
| 量(Activity) |
|
|
| 質(Quality) |
|
|
これらの「量」と「質」に関するデータは、統合ERPのような全社的な情報基盤と連携することで、その価値を最大化します。営業部門の活動データが、リアルタイムで経営指標に反映されることで、経営層はより迅速かつ正確な意思決定を下すことが可能になります。量と質の両輪を回し続ける仕組みこそが、企業の競争優位性を確立するのです。
予材管理を仕組み化するおすすめツール・テンプレート
予材管理は、一度導入して終わりではなく、継続的に運用し、改善を繰り返すことで初めてその効果を最大化できます。
しかし、日々の営業活動の中で、予材の情報を手動で更新し続けるのは大きな負担となり、形骸化してしまうケースも少なくありません。そこで重要になるのが「仕組み化」です。
ここでは、予材管理を効率的かつ継続的に行うための代表的なツールとテンプレートについて、それぞれの特徴を解説します。自社の規模や成熟度に合った方法を選択することが、成功への第一歩となります。
ERPやSFAと連携した統合型予材管理
中堅企業以上の規模で、営業部門だけでなく全社的な視点で成果を最大化したい場合、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)を中核とし、さらにERP(統合基幹業務システム)と連携させた統合型の予材管理が極めて有効です。
SFA/CRMが予材管理の中核を担う理由
SFAやCRMは、顧客情報、商談履歴、活動内容といった営業活動に関するあらゆる情報を一元的に記録・管理するためのプラットフォームです。これらのツールを活用することで、個々の営業担当者が持つ予材(見込み案件)が自動的にデータとして蓄積され、チーム全体でリアルタイムに可視化されます。勘や経験に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて予材の「量」と「質」を正確に把握できるため、予材管理の基盤として最適なツールといえます。
ERP連携で実現する全社最適の予材管理
SFA/CRMが営業現場の最前線のデータを管理するのに対し、ERPは会計、販売、生産、在庫といった企業経営の根幹をなすデータを管理します。この二つを連携させることで、予材管理は新たな次元へと進化します。例えば、SFA/CRMで管理されている受注見込みの高い予材データをERPの生産計画や在庫管理に反映させることで、機会損失の防止や過剰在庫のリスク低減に繋がります。また、予材が売上として計上された後も、ERP上で債権管理や入金状況までをシームレスに追跡できるため、営業から経理まで一気通貫した精度の高いキャッシュフロー予測が可能になります。これは、Excelなど部門ごとに最適化されたツールでは決して実現できない、統合型システムならではの価値です。
Excel・スプレッドシートで作るシンプル予材管理表
専用ツールを導入する前に、まずは予材管理の考え方をチームに浸透させたい場合や、比較的小規模な組織においては、ExcelやGoogleスプレッドシートを活用する方法も有効な選択肢です。
手軽に始められる管理手法
Excelやスプレッドシートの最大のメリットは、多くの企業で既に導入されており、追加コストなしですぐに始められる手軽さにあります。使い慣れたインターフェースであるため、新しいツールの操作を覚える必要がなく、現場の抵抗も少ない傾向にあります。まずはこの手法で予材管理の基本サイクルを回し、その効果を実感した上で、本格的なツール導入を検討するのも良いでしょう。
予材管理表に含めるべき必須項目
効果的な予材管理を行うためには、管理表に含めるべき項目を事前に定義しておくことが重要です。以下は、基本的な項目の一例です。
| 分類 | 項目例 | 管理する目的 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 案件名、顧客名、担当者名、発生日 | どの案件かを特定するための基礎情報 |
| 予材の量 | 見込金額、目標達成への貢献度 | 目標達成に必要な予材の量を定量的に把握 |
| 予材の質 | 受注確度(A,B,Cなど)、商談フェーズ、顧客の課題、キーパーソン情報、競合情報 | 案件がどれだけ受注に近いかを定性的に評価 |
| 進捗管理 | ネクストアクション、アクション期日、最終更新日 | 案件の停滞を防ぎ、着実に前進させる |
予材管理に関するよくある質問
予材管理を実践する上で、多くの企業担当者が抱える疑問や課題があります。ここでは、予材管理に関するよくある質問とその回答をまとめ、より実践的な理解を深めます。
予材管理はどのような業種・業界に向いていますか?
予材管理は、特に法人向け(BtoB)の営業組織で大きな効果を発揮します。具体的には、以下のような特徴を持つ業種・業界に適しています。
- 検討期間が長い商材:システム開発、コンサルティング、不動産、建設、製造業の大型設備など、顧客が導入を決めるまでに時間を要する商材は、予材として長期的に管理・育成するアプローチが有効です。
- 複数のプロセスを経る営業:初回アプローチからヒアリング、提案、クロージングまで、営業プロセスが多段階に分かれている場合、各段階を予材として可視化することで、ボトルネックの特定や改善がしやすくなります。
- 顧客との関係構築が重要な業界:継続的な取引やアップセル・クロスセルが売上の多くを占める業界では、将来の売上候補である「白地」顧客の開拓・管理が事業の安定に直結します。
一方で、店舗での販売が中心となる小売業など、個々の取引が短時間で完結するBtoCビジネスでは、予材管理の概念が馴染みにくい場合があります。しかし、法人営業部門を持つ企業であれば、業界を問わず応用が可能です。
予材管理の「予材」には、具体的にどのようなものが含まれますか?
予材とは、将来の売上につながる可能性のあるすべての材料を指します。 一般的に、受注確度に応じて「見込み」「仕掛」「白地」の3つに分類されますが、その具体的な内容は以下の通りです。 この分類を組織で統一することが、予材管理の第一歩となります。
| 分類 | 具体例 | 管理のポイント |
|---|---|---|
| 見込み |
|
失注しないよう、クロージングに向けたきめ細やかなフォローが重要。受注確度を定期的に見直し、売上予測の精度を高める。 |
| 仕掛 |
|
顧客の課題やニーズを深く理解し、信頼関係を構築するフェーズ。「見込み」に引き上げるための戦略的なアプローチが求められる。 |
| 白地 |
|
将来の「仕掛」や「見込み」を創出するための源泉。定期的な情報提供やアプローチを継続し、関係を途切れさせないことが重要。 |
予材管理が失敗する主な原因と対策を教えてください。
予材管理の導入がうまくいかないケースには、いくつかの共通した原因があります。 主な失敗原因と、それに対する実践的な対策は以下の通りです。
原因1:目的が曖昧で、現場の理解が得られない
「なぜ予材管理を導入するのか」という目的が経営層と現場で共有されていないと、「単なる管理強化」「入力作業の増加」と捉えられ、形骸化してしまいます。
対策:導入の目的(例:売上の安定化、営業プロセスの標準化)を明確に伝え、成功事例を共有するなど、予材管理が現場の営業担当者にとってもメリットがあることを丁寧に説明し、組織全体の共通認識を醸成することが不可欠です。
原因2:マネジメントが機能せず、ただの「報告会」で終わる
定期的なレビュー会議が、単に進捗を報告するだけで終わり、具体的な改善アクションに繋がらないケースです。これでは、予材の「質」と「量」の改善は進みません。
対策:マネージャーは、報告された数字の背景にある課題を深掘りし、「どうすれば見込みに上がるのか」「白地を増やすために何ができるか」といった未来志向の議論を主導する必要があります。具体的なKPIを設定し、データに基づいた客観的なフィードバックを行うことが求められます。
原因3:ツール導入が目的化してしまう
SFA(営業支援ツール)などのITツールを導入しただけで、予材管理が実践できていると満足してしまうケースです。ツールの入力が徹底されず、データが不正確であったり、蓄積されたデータが活用されなかったりします。
対策:ツールはあくまで予材管理を効率化するための「手段」であると位置づけ、入力ルールの徹底やデータ活用方法のトレーニングを行うことが重要です。 現場の負荷を考慮し、シンプルで使いやすいツールを選定することも成功の鍵となります。
Q4 予材管理とSFA/CRM、ERPはどのように連携させるべきですか?
予材管理のポテンシャルを最大限に引き出すためには、SFA/CRMやERPといった基幹システムとの連携が極めて重要です。これらのシステムはそれぞれ異なる役割を担っており、連携させることで経営情報の分断を防ぎ、全社的な視点での意思決定を可能にします。
- SFA/CRM(営業支援/顧客関係管理システム):営業活動の最前線で「予材」を創出し、管理するためのプラットフォームです。顧客情報、商談の進捗、活動履歴などを一元管理し、予材の可視化とトラッキングを実現します。
- ERP(統合基幹業務システム):会計、販売、在庫、生産など、企業全体の基幹業務データを統合管理するシステムです。過去から現在までの「実績」データを正確に把握し、経営状況を可視化します。
SFA/CRMで管理される「未来の売上(予材)」と、ERPで管理される「過去・現在の売上(実績)」をデータ連携させることで、精度の高い売上予測や経営分析が初めて可能になります。 例えば、過去の受注実績データ(ERP)を分析し、受注しやすい顧客層や成功パターンを特定して、今後のターゲティング(SFA/CRM)に活かすといった戦略的な活用が実現します。情報が分断された状態では、こうした高度なデータ活用は困難です。
中小企業やスタートアップでも予材管理は導入すべきでしょうか?
結論から言えば、リソースが限られている中小企業やスタートアップこそ、予材管理を導入すべきです。 大企業のように潤沢な広告宣伝費や人員を投入できないからこそ、一つひとつの営業機会を最大限に活かし、効率的に売上目標を達成するための羅針盤が必要となります。
最初から高機能なツールを導入する必要はありません。まずはExcelやスプレッドシートを用いて、「見込み」「仕掛」「白地」の3分類で案件を管理することから始めるだけでも、以下のようなメリットがあります。
- 営業活動の可視化:今どれくらいの売上見込みがあり、目標達成のためにあとどれだけのアクションが必要か、チーム全員が客観的に把握できる。
- リスクヘッジ:「見込み」案件が失注した場合の備えとして、「仕掛」や「白地」がどれだけあるかを確認でき、精神的な余裕を持って営業活動に取り組める。
- 組織的なノウハウの蓄積:個々の営業担当者の頭の中にあった案件情報が共有され、組織としての営業力が向上する。
事業が成長フェーズに入り、管理する情報量が増えてきた段階で、SFA/CRMやERPといったツールの導入を検討するのが現実的なステップと言えるでしょう。
まとめ
本記事では、営業成果を必然的に高めるためのマネジメント手法「予材管理」について、予実管理との違いから具体的な実践ステップ、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。
予材管理は、目標達成を運や個人の能力に任せるのではなく、未来の売上につながる「源泉」を科学的に管理することで、組織全体の営業力を底上げする考え方です。目標から逆算して必要な予材量を確保し、その質を高める活動を継続的に行うことで、安定した成果創出が可能になります。
成功の鍵は、ご紹介した5つのステップを参考に、まずは自社の営業プロセスを可視化し、チームで共通の基準を持つことから始めることです。そして、SFAやCRMといったツールを活用して管理を仕組み化することで、より効率的かつ継続的な運用が実現します。
さらに、営業活動のデータを販売・会計といった企業の基幹情報と連携させることで、予材管理の精度は飛躍的に向上します。ERP(統合基幹業務システム)のような仕組みを活用すれば、営業部門だけでなく、全社的な視点での正確な売上予測や経営判断が可能になります。これからの時代に求められるデータドリブンな営業組織を構築するためにも、まずは自社の課題と照らし合わせ、ERPがどのように貢献できるか情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。
この記事が、貴社の営業組織をより強く、たくましく変革させるための一助となれば幸いです。